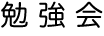
「気候変動の影響と、アジアそして日本の取り組み」
三村 信男さん
茨城大学地球変動適応科学研究機関
2007年7月31日開催
於:ニューヨーク日本政府国連代表部会議室
国連日本政府代表部/国連フォーラム共催 合同勉強会

■ はじめに
■1■ IPCCの評価報告書
■2■ IPCC第四次評価報告書
■3■ アジア・太平洋地域沿岸域への影響と適応策
■ 質疑応答
■ はじめに
今年に入って、温暖化問題ではさまざまな動きがあった。2月、「気候変動に関する政府間パネル」(International Panel on Climate Change, IPCC)の第四次評価報告書は、温暖化が確実に起こっていることが科学的に証明されたと結論づけ、国際的に大きな影響を与えた。6月のG8サミット(ハイリゲンダム・サミット、ドイツ)では、安倍総理大臣が2050年までに世界全体の温室効果ガスを半減させることを提案。また、今年の12月にはインドネシアのバリ島でCOP13(Conference of the Parties to the Climate Change Convention)/MOP3締約国会議が予定されている。来年のG8サミットは日本が開催国であり、そこでも温暖化問題が議題となることが予想される。このように、温暖化問題は国際政治、経済に大きな影響を与えている。
IPCCは、1988年に世界気象機関(World Meteorological Organization, WMO)と国連環境計画(UN Environment Programme, UNEP)により設立された。
IPCCには三つの作業部会があり、気候変動、影響、適応および緩和方策に関し、既に発表された論文の包括的な評価を行い、報告書を発表している。報告書の作成には通常約4年を要するが、第一次評価報告書はたった2年間の作業を経て1990年に発表された。当時は環境問題に関する体系的な研究があまりなく、非常に精力的に既存の研究分析が行われた。この報告書は「温暖化の影響は非常に大きく、早急に対策を講じるべきである」と指摘し、これが引き金となり、1992年、リオ・デ・ジャネイロ(ブラジル)で開かれた地球サミットでは「温暖化防止条約」(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)が締結された。
第二次評価報告書(1995年)と第三次評価報告書(2001年)は、第一次報告書の結論を最新の科学的根拠で裏づけた。第三次報告書は、アメリカが京都議定書からの撤退を表明したため、京都議定書の発効が危惧された時期に発表された。第四次報告書は、ちょうど京都議定書の第一約束期間(注:議定書で定められた温室効果ガス削減への取り組みの第一段階にあたる2008-2012年のこと)が始まる1年前にあたる今年、2007年に発表され、ポスト京都議定書の交渉を考えなければいけないという、タイミングの良い時期に出された。
こうして温暖化問題の対策の歴史を辿っていくと、科学者による論理、根拠の整理と国際的な取組みが歩調を合わせて進んできた。IPCCの報告書作成そのものは科学的なプロセスだが、現実の国際政治・経済に影響を与えることができ、相互関係が成り立っている。
次にIPCCの第四次報告書の作成過程について説明したい。報告書が発表される4年前の2003年に、まず報告書の内容および範囲を決めるための作業部会(Scoping Workshop)が開かれた。報告書の作成に関わる科学者は、各国政府から推薦された数千人の中からIPCCの事務局が各候補の研究実績などを検討し、指名する。指名された科学者は、2004年から三つの作業部会に分かれて報告書作成の作業を進めてきた。報告書は、各作業部会が作成する1,000ページを越す分厚い報告書と20から30ページ程度の政策担当者向けの要約(Summary for Policy Makers, SPM)から成っている。SPMは、110か国300人の政府代表がメンバーとなっているIPCCの総会によって承認される。
私は、温暖化の影響予測、適応策、脆弱性を評価する第二作業部会に執筆責任者として参加した。この作業部会には、他の執筆責任者、編集者などを含め200人あまりが参加した。執筆責任者は、2004年9月から2006年9月にかけて報告書のドラフトを作成。政府担当者と専門家がこれを精査し、それに基づいて執筆者が修正を加える。この作業を4回繰り返した。ドラフトはIPCCの全参加国に回るので、ひとつの章に関して300から1,500くらいの大量のコメントが付され、執筆責任者はそれぞれのコメントに対する見解を残さなくてはならず、非常に大変な作業だった。
2007年3月に第二作業部会の22ページのSPMのドラフトが出来上がった。このSPMを承認するための総会は、2007年4月2日から5日までの4日間で行われた。総会では、図表も含めて一文ずつ承認を求めるのだが、ひとつの文について多数の意見が出され、それぞれについて議論が行われた。総会では全会一致が原則のため、一か国でも反対するとその文章は承認されない。会場では段落、章ごとに執筆責任者が前に座り、300人の政府代表者からの質問に答え続けるので、非常に時間がかかった。そのため、総会の初日に承認されたのはわずか20行。二日目の4月3日は夜10時まで議論し1.5ページが承認された。三日目の4月4日の時点でも、まだたった5ページしか承認されていなかった。
議長はいろいろな工夫を凝らして、議事を進めようとした。例えば、承認の達成度と会議の残り時間を横並びで示し、いかに限られた時間で効率的に議論を進める必要があるかを認識させようとした。また、最終日の夜中の3時に強硬な意見が出、議事が進まなくなった時、議長は全体会議を中断し、小さなグループに分けて交渉を続けさせた。
こうした長い議論と交渉の末、4月6日の午前10時半に漸くSPMが最終的に承認された。第二作業部会の議長のマーチン・パリー博士は記者会見で「われわれは重要な中身を随分失ったが、明らかにするべき評価の本質はすべて報告書に盛り込まれている」と率直に語った。
第四次報告書は、過去にない非常にはっきりしたメッセージを打ち出した。主要な結論は:
- 地球温暖化が起きていて、その影響がすでに環境に現れている。
- 近年の温暖化は人為的な温室効果ガスの増加が原因。
- 将来は更に厳しい影響が予想されている。
- 影響を避けるために適応策が不可欠。しかし、適応策だけでは悪影響は抑止できないので、緩和策との組み合わせが必要。
- 温室効果ガスの排気は増大しつつあり、今後数十年見続ける。現在われわれが持っている、あるいは将来開発可能な技術と政策を組み合わせると安定化は可能である。
地球の平均気温は1000年ほど前(平安時代)から、多少のぶれはあったものの安定的に推移してきた。ところが、20世紀(特に1970年代以降)に入ると気温が急に上がり始め、過去100年で地球の平均気温は摂氏0.74度上昇している。その影響で海面は過去100年で17センチ上昇し、現在も年間3ミリずつ上昇している。その他にも北極の氷の面積が過去数十年で20%減った。一万年前から安定的に推移してきた大気中の炭酸ガスやメタンのような温室効果ガスの濃度は20世紀に入ると280ppm (100万分, Parts Per Million)から380ppmへと急激に上昇している。
人為的な原因によって温暖化がおこるということは、科学者が開発した気候モデルによって裏付けられている。現在、気候モデルは20種類あるが、それらすべてに同じ条件で気候変動を再現計算させてみる。先ず、過去に人間活動による炭酸ガスの排出はなかったと仮定し、つまり自然の温室効果ガスの変動だけを計算する。次に、人間活動と自然変動、両者を合わせて計算をする。この計算結果を実際の気温変動に照らし合わせると、後者の条件で再現計算した気温と重なる。つまり、現在起きている急速な温暖化は人為的な原因によってもたらされたということだ。
将来の温暖化の影響を予測するためには、シナリオ分析を用いる。具体的に将来の社会経済のシナリオをいくつか設定し、各シナリオでどれくらい温室効果ガスが排出されるか計算する。シナリオは6つあり、以下に分類される:
- 高成長社会:化石燃料を使い続け、成長を優先する経済活動とグローバライゼーションが更に進む社会
- 持続発展型社会:グローバライゼーションが進むが、環境保全を重視する経済活動が行われる
- 多次元化社会社:環境保全を優先する経済活動と地域のブロック化が進む
その結果、平均気温は2100年までに1.8度(持続発展型社会の場合)から4.0度(高成長社会の場合)の範囲内で上昇すると予測される。そして、各シナリオによって、将来の気温上昇の地域分布を予測できる。地域的には北極の気温上昇が一番激しいことが分かった。日本の気温も上昇し、今まで真夏日は年間60日程度で推移していたが、このまま温暖化が進むと、2100年までに真夏日はその倍、年間120日にまで増加すると予測されている。温暖化のもうひとつの影響は集中豪雨型の雨が増えることだ。総降雨量が増え、一方、無降雨期が増えることになる。日本ではそのような傾向がもうすでに現れている。
気温上昇の危険な水準についてだが、これは産業革命の平均気温より2度高い気温だ。2度を超えると気象が急激に変化し、そのため特に水不足や感染症などで亡くなる人が大きく増加することが、2000年に行った研究で判明した。これを根拠に、現在各国は、温度の上昇の上限を2度として、これを上回らないような対策を取ろうとしている。

温暖化、気候変動、異常気象という物理的な変化は、水資源、生態系、沿岸の防災、農業、人間活動など、徐々にわれわれの世界に影響を及ぼす。私は海面上昇や沿岸の専門家であるので、その分野に絞って温暖化の影響と対策について説明したい。
沿岸域への影響は大きく(1)自然環境への影響と(2)人間社会への影響に分けることができる。アジア・太平洋の途上国の具体的な例を見てみよう。
(1) タイ
タイの首都バンコクの中心にはチャオプラヤ川が流れている。現在のバンコクは海岸に近いが、バンコクから85キロ北にあるアユタヤという街は、首都であった約千年前には海岸のそばにあった。つまりチャオプラヤ川は現在のバンコクにいたる85キロ以上の距離を自ら運んだ土砂で埋め立てた。
バンコクの西側の海岸は過去15年間で700m後退した。タイの沿岸部には豊かなマングローブの森があるが、その中に住む住民に大きな影響を与えている。この地域の住民の交通手段は船で、家の玄関も店も水の中にある。写真ではマングローブの川沿いに電柱が立っているが、マングローブが後退し海岸線が侵食した場所では、電柱が海の中に残される光景も見られる。残念ながら正確なデータがないため、マングローブの森が後退した原因が温暖化による海面上昇かどうかは分からない。他に原因として考えられるのは、チャオプラヤ川の上流にダムができたために下流に栄養分を含む土砂が流れ込まなくなったこと。もうひとつは、1970年代にバンコク周辺の開発が進み、非常に激しい地盤沈下が起こり、海と陸地の相対関係から海面が上昇したことである。
(2) バングラデシュ
バングラデシュの国土は、もし海面が1メートル上昇すると15%ほど海面下に沈没するという低い所にあり、また非常に強い台風に襲われる。1970年の大きな台風では、高さ6メートルから9メートルの巨大な高潮が発生し、30から50万人の死者が出た。日本が今まで経験した一番高い高潮は3.6メートルで、その時の死者数は5000人であるから、このバングラデシュの被害がいかに大きいかが分かる。バングラデシュは1991年にも強い台風に襲われ、それ以降、台風への対応策を援助するための非常に大きな国際的プロジェクトが立ち上がった。対応策のひとつの例は、レーザーでサイクロンの動きを観察し、それを人々にラジオで知らせるという早期警戒体制の導入である。また構造物による対応として、サイクロン・シェルターという建物を全国で3500ほど建設した。この建物は普段、小学校や集会場として使われ、サイクロンが襲うと、1000人から1200人くらいが避難できる。これらの対策は非常に大きな成果を上げ、1991年以降は(あまり大きな台風が来なかったものの)死者が10万人を超す規模の被害はない。
(3) モルジブ
モルジブのマレ島は防波堤で囲まれている小さな島だ。マレ島の周辺はもともと浅いサンゴ礁だったが、人口が増えるに従って、サンゴ礁を全部埋め立て、人が住む場所にしてしまった。サンゴ礁は天然の防波堤であり波はそこに入ってくると、どんどん消えていく。ところが、このサンゴ礁を全部埋め立てたので、荒い波が直接島を襲うようになった。そのため、マレ島は日本の援助を受け13年かけて島の周りに護岸壁を建設した。この護岸壁が2004年のインド洋津波の時に非常に役立った。津波は震源地から伝わってきて、3時間後にモルジブに到達した。モルジブの防波堤がない小さい島では大きな被害が起きたが、マレ島では、津波の力が最前線で当たった防波堤がいろいろな場所で壊れたものの人的被害はまったくなかった。
(4) 南太平洋の島国:ツバル
ツバルはアトール(環礁の島)で、人口が10,000人しかいない。2000から3000メートルの海底からひょっこり出ている紐のような驚くべき地形の島だ(スライド58)。ツバルの島の下を海水が行き来しているが、その海水にぽっかり浮くように地下水がある。この地下水に頼って、ツバルの人たちが生活をしている。ところが、海面が上がると、地下水が塩水化する。最近、ツバルの最後の井戸がついに使えなくなったという。
ツバルでは侵食が進んでいるため、洪水が良く起こる。また、ツバルならではの現象だが、毎年2月から3月にかけて、潮位が非常に高くなると、サンゴ礁は水が通りやすいため、海水が地面から沸いてくる洪水が起こる。
アジア・太平洋の途上国で調査や研究を通じて、そこの住民は生活の質自体はそんなに悪くなく、逆に満足した生活を送っていると思った。ところが、自給自足経済が発達しているため、温暖化への対応策を取るのに必要な資金がなく、そういう意味では貧しいという国が多い。例えば、侵食が進んでいるので、日本みたいに護岸壁を作ろうと思っても、セメントを買うのが一番大変。そういう国にとって、自然のシステムを維持することは侵食対策上、非常に重要である。サンゴ礁という絶妙な防波堤と、マングローブの森が海岸沿いにあると、荒い波が襲っても、砂浜まで被害をもたらすことがほとんどない。以前、私は侵食に困っている島の人たちにその防止策のアドバイスを求められ、マングローブを植えることを薦めた。その人たちがマングローブを植えてみたら、侵食が見事に減った。自然のシステムを維持しながら、どうしても必要な場所に近代的な護岸壁を建設し、それでも海岸線を守れない場合は、村を海岸線から下げたり(Set-back)、高い所に移したり(Set-up)することで、途上国は海岸侵食に対するさまざまな防止策と適応策を行える。

国際的な対応と適応策
全世界の二酸化炭酸ガスの排出量は増加している。特に中国の排出量の上昇率が高く、今年中にもしかするとアメリカを抜いて、世界一の炭酸ガスの排出国になるかもしれない。今まで、先進国の炭酸ガスの排出量が途上国よりも圧倒的に多かったが、2010年くらいには先進国と途上国が出す炭酸ガスの比率がほぼ同じになると予測されている。
地球の平均気温を危険な水準(2度)以下に抑えようとすると、炭酸ガスの濃度を500から550ppmより低い水準に抑える必要がある。そのために、2050年までに温室効果ガスを、我々が現在出している量の50%以下、そして今世紀末までに25%以下の水準に削減する必要がある。これが安部総理大臣がドイツのハイリゲンダムで開かれたG8のサミットで提唱した「2050年までに少なくとも50%の温室効果ガスの削減」の根拠になる。
温暖化問題の対策には2つの方向がある。先ずは温暖化の進行を止めるという「緩和策」。人間活動から温室効果ガスが排出され、大気中に溜まり、温暖化、気候変動、海面上昇などの悪影響を起こすという一連のプロセスがある。悪影響を防止するというのは、原因となる人間活動を抑えるのと、資源やエネルギーをより効率的に使うということである。緩和策について、1992年の温暖化防止条約以来ずっと議論してきて、そのための技術を開発してきた。ところが、緩和策の効果が現れるのに時間がかかるので、今後、急激に起きてくる温暖化の悪影響から社会を安全に守っていく対策(適応策)も必要だ。
我々は地球システムに関して、理解が非常に深い。地球の中で炭素がどういうふうに回っているのか、それが気候にどんな影響を与えていくのかということに関して、膨大な観測やモデリングの努力をしてきて、これが大きな科学的分野にもなっている。今度はその理解に基づいて、地球問題の緩和策と適応策をどううまく組み合わせ、政策化していくかと問題を解決しなければいけない。
適応策には以下の方法がある:
- 悪影響の発生可能性の低減(予防)
- 悪影響の緩和
- リスクの回避
- リスクの分散(例えば、保険)
- リスクの受容(対策をしない)
問題は適応策を打つ力が社会のどこにあるかということである。アメリカや日本のような先進国は、経済的かつ人的な資源が十分に備わっていて、技術も発達している。温暖化の悪影響が現れそうになったら、資金と技術を投入し、堤防を作ったり、新しい農業のやり方を考えたりして対応をするだとう。先進国は、別の目的で使える資金を、温暖化への対応に使わざるを得ない、という悪影響しか受けない。ところが、途上国は資源と技術がないので、自国を温暖化の悪影響から守るのが非常に難しい。だから、途上国は、資源、人的資源、情報管理、技術、社会制度などすべての社会的資源を強化することで、適応力を高めていく必要がある。
近年、世界的に自然災害による死亡率が増えている一方で、日本ではその死亡率が減ってきた。戦後直後、日本では年間の自然災害による死亡率は100,000人に一人だったが、現在は1,000,000人に一人以下の死亡率まで下がった。それは、1959年に津波の被害で5000人以上の死者が出て、これが引き金となり、政府と地方自治体が一体となって、海岸や河川の堤防の強化を行ってきたからだ。40年かけて、災害による人口当たりの死者を僅かな水準まで下げることができたのが、適応策の効果である。適応策は、効果がすぐに出るというようなものは勿論あるが、日本の例で分かるように、多くの場合は長いリードタイムが必要がある。
今後の課題としては、将来の気候とその影響をより正確に予測するということである。現在は、気候モデルの荒さは一番細かいもので100キロに一つのオーダとなっている。ところが、10キロに一つのオーダにならないと、現実的に気候変動の影響を予測できない。そのために、今の気候モデルの何100倍の能力を持ったようなコンピュータを開発しなければいけない。また、気候変動の影響予測ができると、それを政策に生かし、社会の中ですぐに実行していける一連のプロセスを作る必要である。
皆さんの手元に「気候変動への適応の分野における開発途上国支援」というレポートがあるが、これは、外務省が適応策の基本的な考え方や国際的な枠組みについて、日本の考え方を発信しようということで、有識者会議を準備して下さって、作成したものだ。このレポートの主要なメッセージは、人間の安全保障と持続的な開発にとって、適応策というのは非常に必要な分野であり、その鍵となるのは、社会全体の適応力をどう強化するかということである。「適応にお金を使えば、開発にお金が回わらない」という人もいるが、われわれは適応と開発の効果は同じ方向に働くので、開発の事業の中に気候変動の要素を取り入れることが重要だと考えている。しかし、温暖化に対する、世界でひとつの共通の処方箋はない。その影響はぞれぞれの地域ごとに異なるので、それぞれの地域社会の状況を個別に勘案する必要がある。
気候変動への適応はIPCCという国際の舞台で検討されているが、日本の大学でも研究されている。IR3S(サステイナビリティ学連携研究機構)という大学間の研究連合が2005年に設立され、茨城大学を含め、日本の著名な大学が11校参加している。IRS3は地球環境と社会の持続可能性を確立するために必要な学術(サステイナビリティ学)を研究しているが、その一環として、気候変動への適応も取り上げられている。同年に、茨城大学でICAS(地球変動適応科学研究機関)という学内共同教育研究施設を設立し、私がその責任者となったが、そこでも気候変動への適応策を広範な視点で研究している。
議事録担当:穴井


