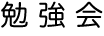
第26回 「イラク戦争後の安全保障理事会の役割:可能性と限界」
川端 清隆さん
国連政治局安全保障理事会部 政務官
2006年11月2日開催
於・UNDP
■Q■ 北朝鮮の核ミサイル発射を機に、日本もようやく自らの安全保障問題として安保理での議論に参加しなくてはいけなくなったとのことだが、日本は今年10月まで安保理の議長国を務めていた。安保理の議長国となることにメリットはあるのか。保理の議論は外部、または国連内部の他の機関にどこまで公開されているのか。
■A■ 本来的には、議長国であっても、その他の理事国との間で影響力に大きな差が出ることはなく、決議案や議論の内容に関して実質的な権限を持つことはできない。もっとも、決議案を出すタイミングを調整したり、決議案を審議する順番を決めたりなど、議長国には手続き的な点での裁量は与えられている。ただし、今回の北朝鮮に関する決議のように、決議を発表する時期そのものが重要な意味を持ってくる場合はその限りではなく、議長国が決められることではなくなる。

■Q■ 冷戦下では拒否権のために安保理が全く機能していなかったが、冷戦終結後、拒否権の意義はどのように変わったのか。
■A■ 冷戦後には、拒否権発動の絶対数そのものが少なくなった。ただ、拒否権はやはり依然として隠然たる力を有している。たとえば、北朝鮮のミサイル発射に対する決議に関しても、ロシアと中国の意向を無視するわけにはいかなかった。拒否権は実際に発動されなくても、それを持っているというだけで意義がある。他方で、拒否権の発動範囲を狭めるべき、という議論は途上国の間などに常に存在している。心情としては理解できるが、それでも拒否権がなくならないのは、大国間の協調に基づいた集団安全保障体制が国連発足以来60年経った今も変わっていないからである。
国連は常備軍を持っておらず、PKOも加盟国の拠出によって機能している。そもそも国連の予算さえも加盟国の拠出に頼っており独自の財源を持っていない。つまり、事務総長の裁量で自由に使える予算はないに等しい。換言すると、国連はあくまでもintra-governmentalな機関であり、決してsupra-governmentalな世界連邦ではない。そういう現状の中で、たとえば明日どこかで紛争が起き、それに介入しなければならないということになれば、どうしても大国に頼らざるをえない。ルワンダで大虐殺が起きたとき、一般の民間人が組織的に殺されているということ、それを何とかしなければいけないということは誰にでも分かった。しかし、いざそれに対処しようとすると、ルワンダで起きている戦闘状態に対応できる部隊をどこかから持ってこなくてはいけない。すると、それだけ練度が高く、指揮系統や装備がしっかりしている部隊を派遣できるのは西側諸国ということになるが、それらの国々はアフリカの紛争に自国の軍隊を派遣することに躊躇した。そういう政治的状況の中で動いたのがアメリカであり、旧宗主国のフランスだった。アメリカからのプレッシャーを受けて日本もゴマの難民キャンプに自衛隊を派遣した。こと軍事に関しては、やはり常任理事国が動かないと何も進まないことを示すよい例だろう。今回、国連がダルフールに介入できることになったのも、ブッシュ政権が騒いだからこそという背景がある。ダルフールにクリスチャンとムスリムの対立を見るブッシュ政権の支持基盤の一つである南部キリスト教勢力の意向と重なり、ブッシュ政権が「ダルフールで起きているのはジェノサイドだ」と言い切ったことが功を奏したのである。
それでは、どういう状況下であれば常任理事国による拒否権の発動を制限できるか、ということであるが、そのためには、国連を支える大国の裾野を広げ、PKOに協力する国を増やさなければならない。日本、ドイツ、イタリア、インドなどの国々が国連の安全保障の裾野を広げれば、拒否権をなくすことはできないまでも、その行使を制限できるような、常任理事国を超えた多極の時代が来るかもしれない。つまり、「大国間の協調」に基づく国際政治が変われば、常任理事国と拒否権を巡る制度も変わる可能性がある。
■Q■ 1998年に北朝鮮がテポドンを発射した際、日本はなかなか情報を得ることができずに苦労した。常任理事国であればアクセスできる情報も増えると思われるが、だからこそ、拒否権を持たずとも、情報を得るためにまずは常任理事国になることが重要なのではないか。安保理の中と外で、情報量にはどのくらい差が出るものなのか。
■A■ 安保理の理事国かそうでないかによって、得られる情報量は圧倒的に違う。理事国であれば、決議案の起草段階から関与できる。イランの制裁に関する決議案には、今は理事国でないドイツが参加しているが、これは例外的なケース。通常、一般加盟国は他の理事国を通して決議の文言に影響を与えようと試みることしかできない。国連事務局や事務総長室から下りてくる情報の量とスピードにも差があり、まず常任理事国、その次は問題によって非常任理事国・兵員供給国などで、最後に一般加盟国という順序となる。このような優先順位がついてしまうのは、事務局としてもやむをえない。
日本が常任理事国となることについては、日本人一般の外交に対する関心がまだまだ低いことを指摘しておきたい。北朝鮮のミサイル発射と核実験でようやく関心が高まってきたが、それまでは世界各地で起きている紛争は日本人にとって直接的な問題ではなかった。ダルフールで何が起きていようと日常生活には影響がないし、なぜ日本の若者をそんなところに派遣しなければならないのか、と考える人も多かったのではないだろうか。しかし、もし日本が常任理事国になれば、そういった問題にも関与せざるをえなくなる。決議案の作成に携わるということは、その結果にも責任を持つということ。特に常任理事国になれば尚更である。日本が常任理事国になるには、日本人一般の意識も大きく変わらなければいけない。

■Q■ ポスト・ポスト冷戦期において多極化が進むというのは不可逆的な変化なのか、それとも現在ブッシュ政権のイラク政策が難航していることを受けて世論が一国主義に対して批判的な方向に傾いているというだけなのか。いずれにせよ、アメリカに振り回されるという状況は同じではないか。
■A■ 現状は混沌としており、ポスト冷戦期のような一極支配の状況に戻る可能性が全くないとはいえない。しかし、現場にいる以上、何らかの判断を下して行動していかざるをえず、その際に基準の一つとなるのがイラクの現状である。ブッシュ自身もイラクでの結果が自分の進めてきた政策を評価するうえでのバロメーターの一つになると発言している。
■Q■ 先日設置された平和構築委員会は、安保理の現状を変えるのは困難であることを踏まえたうえで、安保理を牽制する機能を持ち、かつ安保理に対して提言を行える存在として期待されているという見方もあると聞いているが。
■A■ 平和構築委員会が設置された実情はそうした見方とは全く逆である。平和構築委員会が安保理に対する外野の反対意見を代弁するためだけの組織であるならば、そもそも平和構築委員会は必要ない。
平和構築は政治的な問題であり、紛争地の人々の間で唯一の真実というものはない。様々な利害が対立する中で措置を講じていかなければならないが、その措置を平和構築委員会はまだ持っていない。平和構築委員会には「牙」も「梃子」も与えられていないという点では総会と全く同じ。そのため、平和構築委員会は安保理を牽制するというよりも、安保理では対応しきれないところをフォローアップするという役割を果たすほうがずっと現実的で、かつ物事がスムーズに進むだろうと考えている。
平和構築委員会のメンバーについても、安保理の中から常任理事国5カ国に加えて2カ国の合計7議席を出している。これに対してブラジルなどは「なぜ常任理事国であれば自動的に平和構築委員会のメンバーになれるのか」と最後まで抵抗していたが、現実には、平和構築委員会を安保理の延長線上に置くためには常任理事国を全て入れざるをえない。次から次へと紛争が起こる中で、軍事色が薄れたものから順次平和構築委員会にフォローアップを委譲していく形を取ることは、安保理としても望ましいだろう。
■Q■ 今後日本が取るべき立場として、平和構築委員会のように、フロントラインではなく後方支援から入っていくという考え方もあるが、やはり他の大国と同様にPKOに貢献するべきなのか。日本のプレゼンスを高めるためにはどのような手段が最も効果的か。
■A■ そもそも軍事・非軍事という枠組み自体が、日本でしか通用しない。日本は得意分野である非軍事分野で活動すべき、という議論があるが、日本で使われている「非軍事」と、国連で使われている「非軍事」は、同じ言葉でも意味が全く違う。根本にある「平和」の定義も違っている。そこまでいったん掘り下げたうえで、共通の土壌に立って日本が何をすべきかを議論しなければならない。そもそもなぜ日本が国連に貢献しなくてはいけないのか、と考える日本人もいる。原点に戻って議論の建て直しをする必要があるのではないか。
■Q■ この10年ほど、確かに人道支援に対する関心は高まっているが、安保理決議の中ではauthorization to use forceという表現が使われており、obligation to use forceという表現が使われたことは一度もない。また、冷戦以後、国連憲章第7章に基づく決議が急増しており、第7章の価値が下がったともいわれているが、他方で、第7章にふれずに強固な措置を取る決議もある。6章型決議と7章型決議の区別が曖昧になってきているのではないか。
■A■ 決議の中で使われている文言だけを捉えることには意味がない。安保理は政治と法をつなぐ接点であり、完全な司法の現場ではないからである。そうした場で生まれる決議は政治の現実に基づいて縫い合わされたもの。その典型例がPKOである。PKOは政治的即興の産物ともいわれているが、それを背後で支えているのが総会であり安保理である。個々の事例を取り出せば、そこには様々な矛盾がある。
この7月のミサイル危機では、日本のメディアでは、「北朝鮮に対して第7章に基づいた決議を採択すべき」という議論があった。日本で第7章およびその中の第41条・第42条がクローズアップされたのはよいことだが、決議の文言はあくまでもコインの一面でしかない。安保理は常に政治と法の間を行ったり来たりしている。明石康氏は「国連は国際社会を映す鏡」とおっしゃったが、安保理はまさに国際社会の栄光と悲惨さの両方を同時に映し出している。決議の文言だけがいかに整っていても、そこに魂が入っていないことは多々ある。
安保理がひとたび団結すれば、大きな力を発揮することができる。しかし、光が濃い分、影も濃い。加盟国の団結が果たせないと、安保理は「張子のトラ」に成り下がることもある。安保理がそのような現状になっていることが誰の責任かといえば、結局は日本も含めた個々の加盟国の責任であるということだろう。
以上
担当:大槻、大仲


