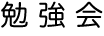
第24回 2006年8月24日開催
於・国連代表部会議室
国連邦人職員会/国連日本政府代表部/国連フォーラム 合同勉強会

「安保理における政治力学−P5(常任理事国)とE10(非常任理事国)」
松浦 博司さん
国際連合日本政府代表部 参事官
(略歴)まつうら・ひろし。昭和62年入省。国際社会協力部人権難民課、総理府国際平和協力本部事務局、経済協力局無償資金協力課、在インドネシア大使館等を経て、2003年より国連代表部政務部勤務。代表部においては、これまで主として、イラク問題、中東和平問題等を担当し、本年1月よりは、安保理改革問題、次期事務総長選出問題、アフガニスタン問題等を担当。
■ はじめに
■1■ 安保理の機能
■2■ 最近の3決議(1695、1696、1701)
■3■ P5とE10
■4■ まとめ
■ 質疑応答
国連日本政府代表部には2003年4月に着任し、2005年末まではイラク問題、中東和平等、安保理を含む国連の政務事項を担当していた。2006年に入ってからは、アフガニスタン、安保理改革等を担当している。着任以来の3年と数ヶ月、特に2005年1月に日本が安保理非常任理事国を務めるようになってからの期間の中で、政務チームの一員として感じたことをお話ししたい。
2006年7月から8月にかけて、重要な決議が3本採択された。これら3本の安保理決議は、安保理のメンバー国15カ国がそれぞれどのように振舞っているか、またP5(常任理事国)とE10(非常任理事国)の間にどのような違いがあるか、ということを知るうえでの好例である。また、安保理は国際の平和及び安全に責任を有する国連の主要な機関であり、国連の中でも特別な地位を持っているが、実際に安保理の中でどのような活動が行われているのかということはあまりよく知られていない。国連憲章を参照しながらこの点についてもみていきたい。
安保理の機能は、世界中で起きている様々な紛争を解決するために、国際社会を代表して介入することである。この「国際社会を代表して介入する」というのは、紛争当事者であるA国とB国の間に、紛争解決に影響力または利害関係を有するC国が介入する、という場合とは異なる。国際社会から委ねられ、その支持を得たうえで、普遍的かつ中立的な立場で正統性を持って介入することが安保理による介入の特徴である。もちろん、紛争によっては、安保理を経ず、影響力を有する国家・国際機関・NGO等が紛争解決のために介入することもあるが、これらのケースと安保理による介入との最大の違いは、後者に対しては普遍性・中立性を帯びることが期待されており、実際にそうなっているということであろう。
安保理の活動は極めて間接的なものばかりであり、(1)決議の採択、(2)声明の発表、(3)安保理ミッションの派遣、に大別できる。このうち安保理ミッションの派遣とは、メンバー国の大使15人が紛争地に赴いて紛争解決のために交渉を行うことであり、唯一直接的であるが、このようなミッションは年に1〜2回程度しか派遣されない。これら間接的な手段ばかりで紛争を収めていこうというのは、改めて考えてみれば無謀なことのようにも思える。安保理の活動は、国連加盟各国の政府、国連事務局、その他の国連機関等がそれを受け入れて行動することで、初めて実効性を持つことができる。
安保理で決定される内容は様々だが、形式としては、いわゆる「決議」にほぼ尽きると言ってよい。内容に関しては、紛争当事者に対して武器を置くよう呼びかける、当該紛争が平和に対する脅威であるとの国際法上の認定を行う、加盟国や国連事務局に対して何らかの活動を行うよう指示する、等が多い。たとえば、A国への禁輸等の制裁措置を行うことを安保理が決定したとしても、実際には、A国との貿易に関与している加盟国の政府が関税等その国の持つ権限を通じて制裁措置を行うということになる(こうした制裁を実施するにあたり、その支援を行うための専門家チームを国連事務局が設置することはある)。制裁措置に留まらず、PKO活動・人道支援・復興支援等を加盟国や国連機関に呼びかける場合にも全て共通している特徴は、活動の主体は安保理ではない、ということである。
安保理が他の平和活動を行う機関と異なるもう一つの顕著な側面は、第一に、国際法上の法的認定を行い、第二に、国連憲章第7章に基づく強制措置を決定する権限を有しているということである。憲章第7章第39条では、安保理の任務として「平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し」と定められている。続く第41条と第42条の強制措置を行うための前提として、第39条による法的認定が行われるのである。強制措置は、第41条の非軍事的措置(経済措置)、第42条の軍事的措置(武力行使)に大別される。
ここで、安保理決議の拘束性と第7章(特に第41条、第42条)の関係、つまり「安保理決議が法的拘束性を持つ場合、それは何に基づいているのか」ということが問題となってくる。憲章第25条が安保理の決定の拘束力について定めているものの、どういう決議であれば拘束力を持つのか、ということが明らかではないからである。この議論に関しては様々な説が出されているが、合意は得られていない。代表的な説としては、以下3つが挙げられる。まず、安保理の内外で通俗的に受け入れられているのは、「第7章に言及している決議には拘束力があり、言及していない決議には拘束力がない」という説である。
次に、法文の観点から合理的であると思われる説は、「Decisionかrecommendationか、という決定の性質に基づいて判断すべき」というものである。第39条において、安保理が行うのは「勧告(recommend)」または「決定(decide)」であると明確に規定されており、第25条の文言をみると、拘束力があることに予め同意されているのは「決定」である。このため、安保理の決議が「勧告」である場合には拘束力を持たないが、「決定」である場合には拘束力を持つ、と解釈するのが合理的ではないだろうか。それでは、どのような決議が「勧告」でどのような決議が「決定」か、という問題であるが、これについては、決議の中で用いられている動詞が「decides」「demands」「requires」「determines」等であれば「決定」であり、これに対して「calls for」「invites」「encourages」等のより弱い動詞が用いられていれば「勧告」であると考えられるだろう。従って、この考え方にたつ場合ある決議が全体としてというよりも、決議の中のそれぞれのパラグラフが拘束力を持つかどうかということを判断していく必要がある。
第三の説は、決議の内容が第41条、第42条に基づく強制措置であるかどうかを判断したうえで、そうであれば拘束力がある、そうでなければ拘束力がない、と考えるものである。この説は一見わかりやすいが、この判断基準にあてはまらない例も多い。たとえば、経済的な強制措置を取ることを呼びかけていても、その性質はあくまでも勧告的であり、加盟国に対して義務を課すものではないという場合がそうである。つまり、強制措置の有無も決定的なメルクマールにはならないと考える。
これら3つの説のうちどれが正しいという決定的な合意はなく、その結果、決議の中で第7章に言及するかしないかが非常に大きな政治的意味を持つようになっている。つまり、安保理のメンバー国が、第7章への言及を政治的ゲームの切り札として多用しているという状況である。他方で、妥協の結果として文言が曖昧な形になることもあるので、文言が持つ象徴的な意味と実際の拘束力に乖離が生じるケースもある。これについてはこれから取り上げる3本の決議の中に好例があるので、後ほど詳しく説明したい。
もっとも、安保理の中で常に緊迫した政治的ゲームが行われているわけではなく、日常の活動には山と谷がある。紛争が起きた際に停戦に向けた活動を行う戦時の介入、または長年続いている紛争であっても急に状況が変化する等、差し迫った状況の中で採択される決議にはそうした状況にふさわしい政治的な重みがあるが、そうした決議ばかりではない。2006年8月の安保理の予定表や、2006年に入ってから採択された決議の一覧をみればわかるように、紛争に対して過去に安保理が決定した活動の進捗状況を国連事務局に報告してもらってそれを審議する等、活動のプロセス確認とその評価を行うことで、安保理が紛争解決に長期的にコミットしていくという姿勢を示す活動も行っている。また、PKO活動を延長する等、手続き的な決議もたくさん採択されている。こうした「谷」の時期においても紛争そのものは継続しているので、「平時」という言い方はやや不適当であるが、あえて対比上「平時」という表現を使えば、メンバー国間の意見の対立が顕在化するような状況は平時においては稀であり、安保理の審議は戦時・平時のコントラストがはっきりしているのも特徴の一つだろう。
しかし、安保理の最大の特徴は、やはりその間接性と普遍性にある。常任5カ国と選挙で選ばれた非常任10カ国の大使が集まって協議を行っているが、それらメンバー国が全て、議題となる紛争の解決に影響力を持っているわけではなく、紛争解決のためのベストプレーヤーがメンバー国として揃っているわけでもない。また、活動の実施を依頼された側が安保理の決議に従わなければ、決議には何の意味もなくなる。安保理決議が意味を持つためには、安保理のメンバー国であるかないかにかかわらず、紛争解決に影響力を持ち、かつその力を行使しようとする意志を持っているプレーヤーが決議の作成に何らかの形で参加することが重要となる。
影響力を持つプレーヤーだけの名前で解決策が発表されたのでは、紛争当事国としてもそれを受け入れ難いという状況もあるだろう。そうした場合に、国際社会の信任を受けた安保理の名前があれば、当事国側も受け入れやすくなる。また、紛争解決のための資源を国連加盟国から動員するにあたっても、多くの場合国際社会を代表する安保理からの要請という形式を取っている方が、加盟国側も行動しやすい事情にある。このような場合、安保理が持つ普遍性の帳は効果を発揮する。真に影響力を持つ国が、様々なプレーヤーの「普遍性に対するニーズ」をくみ取りながら解決策を作り、それに安保理決議が持つ普遍性の帳をかけることが重要である。
他方、インドネシアのアチェ紛争のように、紛争が徒に国際化されることが解決を遅らせるという判断により安保理による介入を行わなかったケースもある。安保理が介入するよりも、事情をよく知るプレーヤーが地道に仲介活動を行った方がかえって早期解決できるケースもあるということである。また、強制措置を行う場合でも、当事者がことさらに普遍性を求めないケースもある。たとえばNATOのコソヴォ空爆は、安保理決議なしに、人道上・政治上空爆が必要とのNATO諸国の判断に基づいて行われたことである。これらのケースをみればわかるように、全ての紛争解決に普遍性が必要なわけではない。従って、普遍性の要不要を見極めることが重要になるが、それを見極めるのは、やはり紛争解決に影響力を持ち、紛争当事国のことを理解しているプレーヤーであろう。安保理決議は、そうしたプレーヤーの意見を反映することができて初めて実効性を持つのである。紛争の現場で影響力を持たない人々が安保理の会議室の中で空論を作り上げても、そのような決議が実効性を持つことはない。
今日は、(1)北朝鮮のミサイル発射に関する決議(1695)、(2)イランにウラン濃縮停止を求めた決議(1696)、(3)レバノン紛争に関する決議(1701)の3本を詳しくみていきたい。これらの決議には、誰が安保理の普遍性を必要としたか、という点で異なっており、決議が持つ拘束性にもバラエティがある。また、メンバー国の議論への参加の仕方も三者三様であった。
(1) 北朝鮮のミサイル発射に関する決議(1695)
この決議は、北朝鮮のミサイル発射は国際環境を不安定にするものであるという前提のもとに、制裁措置を求めたものである。第7章に直接言及することなく、第24条第1項の文言を変形して引用することで処理している。また、決議の中では「demands」「requires」といった動詞が用いられているため、「勧告」というよりは「決定」の性質が強いと読み取れる。他方、強制措置ばかりでなく、北朝鮮に六カ国協議に復帰するよう求め、安保理としてそれを支援することを表明してもいる(主文第6パラグラフ)。議論に反対意見がなく、安保理のメンバー国全員が起草者となる決議のことを「議長テキスト」と呼ぶが、この決議も議長テキストとなっている。これは、決議が全会一致で採択され、一体性を持っているということがより強調されるという政治的効果を持つ。この決議は、日米がドラフトを作成し、日米を中心にして、ある時はP5及び日本、またある時は全15カ国間で議論が行われた。
(2)イランにウラン濃縮停止を求めた決議(1696)
もともとイランとの核開発交渉の窓口になっていたのはEUであるが、この決議は、アメリカが、イランがウラン濃縮を停止すればアメリカとの直接交渉の機会を設けるという交換条件を提示したことを受けて、「濃縮停止」の部分に法的、政治的重みを付加したもの。前文の最後のパラグラフに「Acting under Article 40 of Chapter VII of the Charter of the United Nations」という文言があるが、ここで第7章全体ではなく、特に第40条のみに言及していることに留意してほしい。第40条は暫定措置を定めたものであり、第41条、第42条の強制措置に入る前段階というべきものである。こうしたことから、この文言は政治的な妥協の結果として挿入されたものであると考えられる。
主文の第2パラグラフでは「Demands」という、勧告よりは決定としての性質が強い動詞が使われているものの、第3パラグラフにあるように「diplomatic, negotiated solution」を通じた濃縮停止を求めるという姿勢が確保されている。また、第5パラグラフでは、濃縮活動に寄与するような物資が国境を越えてイランに持ち込まれないようにと国連加盟国に呼びかけているが、これは第40条の暫定措置に該当するものと考えられる。強制措置ではなく、あくまでも暫定措置として呼びかけていることを明確にしていることが、激しい交渉の結果妥協に達したこの決議のポイントであろう。
第7・第8パラグラフでは、IAEAへの報告の提出期限を定め、期限を過ぎてもイランによる濃縮停止が遵守されなければ、第40条を超えて第41条による強制措置に入ると仄めかしている。このあたりは、当初の起草者であった英仏の意図はさておき、ニュアンスに富んだ表現となっている。この決議では、英仏独の共同作成によるドラフトが安保理に提出された後、英仏米間、P5とドイツ間、全15カ国間等様々な顔ぶれによる協議が行われ、P5及びドイツのみの協議と全15カ国による協議が交互に進められた。
 |
| © UN Photo |
(3)レバノン紛争に関する決議(1701)
この紛争が勃発した当初、ヒズボラがイスラエルを挑発したことに対してイスラエルがある程度の反撃を行うであろうことは予想されていた。しかし、イスラエルが思いがけず大規模な爆撃を行い、それに対して安保理が実効的な対応を取れなかったことに国連のアナン事務総長が遺憾の意を表明するという、あまり過去に例のない道を辿った。
前文の第4パラグラフに「Welcoming the efforts of the Lebanese Prime Minister and the commitment of the Government of Lebanon, in its seven-point plan」とある。これは、ヒズボラとイスラエルの間の紛争ではあっても、レバノン政府は主権国家としてそれを許すべきではなく、紛争解決のために尽力すべきであるという文脈の中で、自力で紛争を解決したいというレバノン政府の意志を尊重して挿入されたもの。前文第5パラグラフの「withdrawal」については、当初、ヒズボラとイスラエルは、停戦はするものの、多国籍軍の駐留等によってヒズボラが再び戦争を起こさないと保証されるまでイスラエル軍は撤収しなくてもよいという方向で議論が進んでいたのに対し、レバノン政府がそれを受け入れることを拒否したために挿入された。イスラエルがこの案に同意したのは、レバノン政府が責任を持って政府軍をレバノン南部に展開し、かつそれが確実に実効性を持つよう、UNIFIL(United Nations Interim Force in Lebanon)を増強することを要求したうえでのことである。
なお、前文の最後のパラグラフでは「Determining that the situation in Lebanon constitutes a threat to international peace and security」と述べることで、レバノンにおける紛争が国際の平和及び安全に対する脅威であることを認定している。本来、脅威を認定することの目的は、あくまでも第41条・第42条の強制措置に進むための根拠を明確にすることであり、単に脅威を認定するだけでは意味がないはずである。これには、第7章に言及すれば、主権国家として紛争に対応しようとしているレバノン政府の権威を損ないかねないとレバノン政府が必死に交渉し、その結果、第7章に関する文言が削除されたという経緯がある。
決議の主文では、ヒズボラに対しては全ての攻撃を停止するよう求めているのに対し、イスラエルに対しては攻撃的軍事作戦を停止するよう求めているという非対称性が大きな特徴となっている。主文第2パラグラフはイスラエル軍の撤退について定めているが、ここで「in parallel」という文言が用いられることにより、順次移行の発想が示されている。
長期的な紛争解決を行うために定められた原則の中で特徴的なのは、第一に、非武装地帯を設けるとしていることである。もっとも、レバノン政府軍とUNIFILの駐留は認められており、あくまでもヒズボラが武装したままレバノン南部に留まることを禁止するものである。第二に、この非武装化を「誰が」行うかということは明記されていない。このことは、非武装化はレバノン政府が国内の政治的対話を通じて行ってもよく、すなわち、今回の撤退の過程で実施することを必ずしも求めていないことを含意している。
また、1万5千人のレバノン軍を確保することに加えて、UNIFILの任務を拡大することで、UNIFILがレバノンにおける停戦を監視し、レバノン国軍の南部展開を支援するということが、イスラエルがそれと「in parallel」に撤退するために重要となってくる。UNIFILについては、任務の内容が拡大されただけでなく、第12パラグラフにおいて任務を遂行するうえでの権限も強化されており、必要があれば相当程度の幅広い武器行使が認められている。第7章への直接の言及はないが、定め方としてはそれに近いと判断されても仕方のないような文言が並んでいるといえよう。第15・第16パラグラフは、レバノンに武器が流入しないよう、レバノン政府に武器貿易の管理を呼びかけ、他の国連加盟国に強制措置としての武器禁輸を義務付けるものである。これら全ての条件を加味したうえで、イスラエルは多国籍軍ではなくUNIFILによる停戦監視を受け入れたという経緯がある。
レバノン紛争に関する決議で非常に興味深いエピソードとして、ロシアが短期間の人道休戦を決定するための短い決議を提出したが、他のメンバー国からの支持を得られず、ロシアもすぐにこれを撤回したというものがある。結局、イスラエルとレバノンの双方とも、安保理決議という形式の中で停戦の枠組みが決まることを実は望んでいたために、ここまで粘り強く交渉に応じてきたわけであるが、実際に安保理の中では、アメリカがイスラエルを、フランスがレバノンを代弁する形で協議が行われてきた。もちろん、アメリカもフランスも単なる代弁者としてのみ発言していたわけではないが、ロシアが紛争当事者の立場を代弁していたのではないことだけは明らかである。ロシアが提案した決議の内容そのものには特に問題もなく、メンバー国からの反対も出なかったが、実際に行動に移す段階になれば、イスラエルもレバノンも守りはしないだろう。紛争当事者に本気でコミットしていないメンバー国が決議を提案したとしても結局は実効性を得られず、ただの紙切れになってしまうことの好例といえる。
なお、レバノン紛争に関する決議の交渉は、アメリカとイスラエル間、フランスとレバノン間、米仏間、P5間、全メンバー国間等のパターンを経て、最終的には全会一致で決着した。
これら3本の決議からいえることは、以下の3点である。
第一に、北朝鮮とイランに対する決議は、厳密には強制措置とはいえないものの、それに類似した措置を定めることによって当事者に圧力をかける姿勢が前面に打ち出されている。こうしたパターンの決議は当事者を追い込むことを目的としているため、当事者である北朝鮮やイランは決議交渉の蚊帳の外に置かれていた。安保理決議の普遍性を活用したかったのは、当事者ではなく、むしろ当事者を追い込みたいと考えていた側であった、ということである。逆にレバノンに関する決議では、当事者であるレバノン政府に解決が委ねられ、強制措置である武器禁輸はあくまでも補助的な位置づけとなっているばかりでなく、イスラエルとレバノンが交渉プロセスの中に不可欠なプレーヤーとして組み込まれていた。レバノン、イスラエル双方とも、国際社会から求められたから停戦に応じた、という形をそれぞれの国内に対して整える必要があったため、安保理の普遍性を活用したかったのであろう。
第二に、安保理決議の拘束性がいかに多様であるかということが、わずか3本の決議の中にもはっきりと現れており、一概に第7章への言及をもって判断すべきでないということが改めて確認できる。
第三に、決議の採択に到るまでの交渉のパターンにも様々なものがあるということである。紛争に深く関与しているP5以外のプレーヤーが起草者の一部として大きな役割を果たした一方で、P5による協議も頻繁に行われており、P5の卓越した役割が改めて示される結果となった。

P5といえば、威張っていて圧倒的な存在感を誇示しているという印象があるが、それでいながら実際には、P5が持つ最大の切り札である拒否権を行使するどころか、拒否権の行使を仄めかすことすら、滅多には起こらない。そこにはP5としての自己抑制が効いている、という矛盾した印象を受けている。また、戦時の対応ではP5間で文言に関する交渉が頻繁に行われ、E10は蚊帳の外に置かれるということが多々あるが、これに対して平時の対応ではP5間での交渉という色は薄められ、全15カ国間で協議が進められるという対照的なプロセスが取られる。
日常的には、P5が存在感を示すのは、あからさまに特権や権限を振りかざすことによってではなく、より微妙なやり方によっていることの方が多い。安保理の中で誰がリーダーシップ・オーナーシップを取っているかということは一概には言えないが、フランス、イギリス、アメリカが決議の起案国となる議題数が多く、決議の交渉の場においても必然的にリードを取ることになる。また、決議に対して根本的な問題提起を行い、決議そのものの枠組みに挑戦するのは、ロシア、中国、アメリカ等、やはりP5のメンバーであることが圧倒的に多い。
なぜP5が安保理における議論をリードしているかというと、背景事情は多様である。一つには、安保理のルールや手続きに関する確定的な明文規定がないため、最新の詳しい内容をP5しか知らない、という状況になっていることが挙げられる。E10のメンバーは頻繁に入れ替わるため、手続きに詳しくなるための時間的余裕がない。また、制裁支援、文民警察等といった政策ツールの細部は毎年絶えず変わっているため、運用面にまで精通できるのはやはり常にそれら政策ツールを観察できる立場にあるP5のみ、ということになる。また、交渉を有利に進めるためには、どのような国がどれほど強く出れば拒否権の発動につながるか、どれほどの交渉パターンがあるか、等が皮膚感覚として身についている必要があるが、これはやはり場数を踏んでいなければわからない。またP5は毎月当番を決めて、定例の情報交換を行い、仲間意識を培っている。さらに、P5の国の出身者は国連事務局や現場の枢要ポストを多数占めており、事務局への影響力行使や事務局からの情報収集を通じて、P5のもう一つの力の源泉となっている。また、常に安保理に参加しているP5とたまにしか参加できないE10では、外交当局内部における安保理の経験を経た人材の厚みも違うため、安保理の最新の手続きに詳しい人間が本国、国連代表部、紛争地域の在外公館にどれほど分散しているか、という点でも大きな差が現れる。
それではE10は何をしているかというと、たとえば日本であれば東ティモール、北朝鮮、アフガニスタンのように、特定の地域に関する議論をリードしようとする努力はみせている。もっとも、E10がただ1カ国だけで議論をリードすることには限界があるので、コアグループまたはフレンズ・グループと呼ばれるグループを作り、「一国だけの主張ではない」と議論を補強しながら安保理内での交渉を進めていかなければならない。また、E10には決議の根本的な枠組みを批判することはなかなか難しく、安保理のアラブ出身メンバーの場合のように、外部の有力なグループ(アラブ・メンバーであればアラブ諸国グループ)を背景にしている場合を除いては、リード国が設定する枠組みの中で改善のための提案をするに留まることが多い。
P5とE10の間の力の差は日々感じることではあるが、それは必ずしも拒否権を有しているかどうかに由来しているわけではない。むしろ、常に安保理のメンバーであり続けること、それによるメンバー間の馴染みや歴史の長さに抗し難い重みを感じる。
こうした常任理事国による安保理支配は、単に非常任理事国を悔しがらせる効果を持つばかりではなく、場合により安保理の紛争解決機能に対しマイナスに働く場合も出てくるものと考える。
一点目は、P5による安保理支配の構造が固定化してしまっているため、その専横ぶりにより安保理の権威と信頼性を損ないかねないこと。二点目は、「戦時」における協議に典型的に現れる通り、P5だけで議論を強引に進めて国際社会の各地域を代弁する立場にあるE10を無視しようとすれば、安保理の持つ普遍性を空虚化させてしまい、安保理の決定が真に国際社会を代弁しているのかという疑義を招くことである。三点目は、紛争解決に最も影響力を有するプレーヤーが議論をリードすることが重要であるにもかかわらず、そうしたプレーヤーがメンバー国の中に常に存在しているのか、またP5の外にそうしたプレーヤーがいた場合、そのプレーヤーは十分な力を発揮できるのか、という点で疑問が生じることである。もっとも、P5もこれらの点についてはよく承知しており、P5が安保理を支配することに大きな意義を見出しているからこそ、その権力を濫用せずに自己抑制することで、その特権を維持することに心を砕いているといえよう。とりわけ、「戦時」におけるP5中心の交渉プロセスの代償として、「平時」においてなるべく15カ国対等の交渉プロセスを演出するよう努めているとも言えるであろう。
安保理の平和活動は、安保理自身の行動でみる限り、決議採択という間接的な形式を取っているので、決議の採択にあたっては、紛争当事者や関係者が安保理の普遍性をどう利用するかという政治的駆け引きが大きく影響してくる。P5のメンバーが固定していることにより紛争解決に真に影響力を持つプレーヤーが交渉に参加できない、というデメリットを改善しなければ、安保理決議の実効性は失われかねないだろう。
担当:大槻、大仲、藤澤


