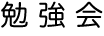
第26回 「イラク戦争後の安全保障理事会の役割:可能性と限界」
川端 清隆さん
国連政治局安全保障理事会部 政務官

2006年11月2日開催
於・UNDP
(略歴)川端 清隆(かわばた きよたか):大阪府生まれ。1979年、米国ミシガン州ホープ大学卒。コロンビア大学大学院政治学部修士。時事通信記者を経て、1988年より国連本部政治局政務官。安保理改組、アフガン和平やイラク問題の処理に従事した後、現在は安保理を担当。著書に『アフガニスタン―国連和平活動と地域紛争』(みすず書房)、共著に『PKO新時代』(岩波書店)。
■ はじめに
■1■ 安保理の現状
■2■ 安保理の拒否権
■3■ ポスト冷戦期における安保理
■4■ これからの安保理
■ 質疑応答
今日は、安保理がどういうところで、どういう仕事をするのか、それが国際社会にとってどのような意味を持っているのか、ということについてお話ししたい。特に、日本の国連観・安保理観とのギャップについても考えて頂きたい。
■1■ 安保理の現状
この夏の安保理の動きには面白い傾向がみられる。6月の終わりから8月にかけて、重要な紛争問題が次々と安保理に持ち込まれるようになった。北朝鮮の核ミサイル問題、イランの核開発問題、レバノン紛争、ダルフールに国連史上最大規模のPKOミッションを派遣するための素案作成、東ティモールの「出戻り」PKO、コンゴにおける国連史上最大規模の選挙支援(第1と第2ラウンド)準備およびそれに関する安保理での審議などである。もっと時間のあるときであれば、この中の問題ただ一つだけをとっても審議に1〜2ヶ月を要するような、そうした大問題が連続して安保理に提出された。
通常、安保理にとって夏は比較的楽な季節で、資料整理などをする充電期間だったが、今年の夏は土日の休みもなくあっという間に過ぎてしまい、今でもまだその状態が続いている。ダルフールに関する決議はスーダン政府の抵抗に遭っており、イラン制裁に関する決議も常任理事国の間で継続審議中である。北朝鮮については、核実験が行われたせいで十月初めの2週間は大変だった。
こうした状況を受け、国連安保理部の中では、9.11テロおよびイラク戦争以降の安保理の役割が節目に来ているのではないか、と語り合っている。今年の夏から秋にかけて、安保理の役割が飛躍的に拡大したということは国連にとって一見いいことのように見えるが、中身をよく見てみると、決してそればかりではない。なぜなら、この傾向は、イラク戦争を未然に防止することができずに失墜した国連の権威が回復したためでは必ずしもないからだ。むしろ、アメリカの一国主義が顕著に衰退したことによるものではないか、という見方の方が強い。
ブッシュ政権は、イラクのように自国の直接の戦略的利害が関わる問題について国連が関与することを否定した。その結果、安保理は真っ二つに割れてしまった。アメリカの思い通りに動かないのであれば安保理はいっそ動かなくていい、という立場を取るアメリカに対して、ロシア、ヨーロッパ諸国、当時の非常任理事国であったドイツは、安保理があってこそ紛争処理が機能するという立場を取ったのである。イラクの戦後処理と復興支援を巡る議論においても、この決裂状態は未だに解決されていない。形だけはイラク復興に関する決議が何本も採択されているが、実は安保理内は完全に分断されている。アメリカが主張するように、戦勝国が復興支援の実権を握って国連は二義的な役割を担うにとどまるのか、それとも国連がアメリカに対してさえもNOと言える力を持つのか、アメリカとヨーロッパ諸国で意見が分裂したままであり、そうした中で、ぽつりぽつりとイラクに対する協力が行われている。イラク戦争の直前までは、800〜900名の国連職員がイラクで巨大なオペレーションを行っていたが、2003年のバグダッド爆撃事件以降、イラクの国連職員はいったんゼロになった。それ以後少しずつ増えて今年ようやく400名程度になったが、それでもピーク時の半数以下でしかなく、しかも厳重な警備の下でしか行動できないので、実質的な復興支援活動はほとんどできていない。
ブッシュ政権下での一国主導体制は少しずつ軋みを見せ始めている。アメリカのネオコンが主張するようなunilateralism(一国主義)ではどうしようもない、という兆候が出てきている。もしもネオコンが夢見ていたように、中東の真ん中に民主主義国が樹立され、民主化のドミノが達成されていれば、イランの核開発や北朝鮮のミサイル発射へのアメリカの対処も違っていただろう。アメリカはもっと単独主義的な対応を取りたかったかもしれないが、今はとてもそうできるような政治的状況ではない。その結果、これらの問題が国連に放り投げられるようになった。
レバノンに関しても、ブッシュ政権は多国籍軍を投入してヒズボラを武装解除し、一気に解決に持ち込みたいという夢を持っていたが、それが実現できず、ああでもないこうでもないと話し合っている間に、ブッシュ政権があれほど忌み嫌っていた国連PKOに任せざるをえなくなってしまった、というのがUNIFIL拡大の背景にある事情。識者の中では、これでようやくアメリカの一極支配が崩れ、多極支配に戻るのではないか、といわれている。これを、冷戦終結からイラク戦争までの、米国が唯一の超大国として圧倒的な力を握った「ポスト冷戦期」からより多極的な「ポスト・ポスト冷戦期」に入りつつあると表現することもできるが、こうした中で、国連、そして安保理の役割は何か、ということが問われている。

以上が安保理の現状であるが、そもそも安保理とは一体何をするところか、ということを改めて考えてみたい。基本に戻ると、安保理が国連の他の組織と顕著に違っている点はただ一点、「今そこにある個別の紛争にどう対処するのか」ということを話し合い、具体的な措置を講ずるための場であるということだ。その結果が決議という形で現れる。安保理は漠然とした平和論を話し合う場ではない。
各国の政治的利害の衝突の結果として採択された決議が国際法上の効力を持つという意味において(国連憲章第25条)、決議は「政治と法の接点」であると表現することができるだろう。もっとも、決議は政治のどうしようもない混沌の中から生み出されたものだが、それでは安保理の決議が全て有効で平和のために役立つかというと、そうでもない。
安保理の中で意見が割れた場合、特に常任理事国から拒否権が発動された場合には安保理は結果を出すことができない。なぜ拒否権が存在するのかということについては、日本ではなかなか理解がされないようにみえる。特に安保理改革に関する議論においては、拒否権の位置づけが正確に評価されていなかった。拒否権が不公平なものであるとネガティブに決めつけるのは簡単であり、「安保理の常任理事国だけにこのような特権が与えられているのはとんでもないことだ」という批判は安保理改革が議論される度に毎回必ず登場する。日本政府は「常任理事国にはなりたいが拒否権はいらない」という立場を採ったが、これでは拒否権についての理解が十分であるとは思えない。常任理事国と拒否権は表裏一体であり、切っても切れない関係にあるからだ。
国連が平和を守るための組織であることは国連憲章前文の冒頭に掲げられている。「戦争の惨害から将来の世代を救う」ことが国連の目的の一つであり、その目的を達成するための中心的存在が安保理である。国連は集団安全保障体制を体現している。しかも、地域ではなく、地球規模かつ世界的な普遍的集団安全保障体制である。この特徴は、1945年の国連発足時の大国、即ち戦勝国の利害が一致し、それに合意に基づく協力(concert
of power)が可能になった場合にのみ機能する集団的安全保障体制である。この「大国間の合意」を担保する唯一無二の制度が拒否権である。拒否権の導入には、スターリンが強固に提唱し、チャーチルとルーズベルトが支持したという経緯がある。拒否権はそもそも常任理事国制と不可分の存在であるため、日本が「常任理事国にはなりたいが拒否権はいらない」と主張することは矛盾している。
このような形で集団安全保障体制を60年間続けてきたわけであるが、冷戦終結後、安保理の役割が大きく変わった。冷戦中は東西イデオロギー対立の抑制と危機管理が安保理にとって唯一最大の目的であった。中東においてもアフリカにおいても、小さな代理戦争が東西対立にエスカレートすることを防ぎ、紛争を局地化することが求められていたからである。パレスチナやスエズにおける中東紛争、(NATO加盟国間の紛争ではあるが)キプロス紛争、アフリカ各地での紛争などが米ソ対立を引き起こしかねない状況下で、それを防止するのが冷戦期における安保理の役割だった。それはそれで必要な役割であったが、大国が直接関わる紛争には安保理は手をつけることができなかった。
たとえば、ベトナム戦争は安保理での議題に上ることすらなかった。ソ連のアフガニスタン侵攻は、議論が始まった初日にソ連が拒否権を発動し、その後安保理では一度も話し合われることがなかった。また、安保理は各地で起きる紛争に対する応急処置を施すことはできても、紛争の根本にある問題を解決することはできなかったし、やろうとしてもできるような体制ではなかった。「平和」に対して東西の陣営が全く違う概念を持っていたため、政治的な議題になると、必ず東西どちらかからブロックがかかった。その一例がパレスチナ紛争であり、キプロスでも膠着状態が30年もの間続いている。
こうした状況が、冷戦終結を機に劇的に変わった。超大国の一方が文字通り消滅し、安保理による紛争解決はナミビアをはじめカンボジアやニカラグアで成功を収めた。これらの国では、甚だ不完全ではあるものの、現在に至るまで紛争の再発を防ぐことができている。また、停戦監視だけではなく、選挙監視、人権保護、NGO育成なども行うようになり、1990年から1991年にかけて安保理の活動は大きく様変わりした。それまでは、これらの言葉を口に出すだけでも、安保理の中でソ連や中国の代表が目の色を変えて反対していたものである。
冷戦の終結はしかし、新たな問題も国連にもたらした。安保理は、国連憲章の起草時には想定されていなかったような問題にも対処せざるをえなくなったのだ。主権国家の中で、民族や宗派の違いを理由として行われる内戦もその一つである。冷戦のくびきが消えると同時に、大国の利害に影響を与えないアフリカや中央アジアの辺境で内戦が頻発し始めた。冷戦期には、こうした小国も東西対立を利用すればアメリカかソ連のいずれかから援助を受けることが可能だったが、東西の対立図式が消えてしまったので、国連が最初で最後の防衛ラインとなるような状況に陥ったのである。ガリ事務総長時代、国連はこれらの内戦に対して積極的に関与しようとしたが、それを担保するだけの法的・制度的体制が国連の方に整っていなかった。国連憲章2条7項で内政不干渉の原則を定めていることからもわかるように、国連は内戦への対応を想定していなかったのである。内戦への対応に関する理念や制度がないだけでなく、何をもってすれば、またどこの時点で国連の役割が終わったといえるのか、ということすらも曖昧である。ネオコンが主張するような「完全な民主化」を目的とするのであれば、カンボジアですらもそれが達成されたとはいえないだろう。また、国連にとっての当事者とは誰なのか。内戦に関しては、「当事者合意の原則」が通用しない。これまでは政府を相手にしていればよかったが、政府が瓦解し、群雄割拠している状況下では、戦闘の勝敗によって交渉相手が日々変わりかねないし、停戦を誰と合意すればよいのかさえもわからない。このような例として、ソマリア、ルワンダ、ボスニア、コソボ、東ティモールなどでの人道的介入を挙げることができる。
過去10年間、国連はこれらの問題に対応するために非常に苦しんだ。10年前には、インドや南アフリカ共和国が「国連が人道問題に携わるのは国家主権の侵害だ」と反対しているような状況だった。この10年間のとてつもない人的な犠牲と試行錯誤の結果、国際社会として、主権国家内といえども大量かつ組織的な人道問題は看過できないということが、ようやく昨年のミレニアム文書において明文化された。ここまでは非常に長い道のりであったが、安保理の役割の変遷を考えるうえで無視することはできない。
 |
| © UN Photo |
これまで、ポスト冷戦期における安保理の役割をみてきたが、こうした流れを、ポスト・ポスト冷戦期における安保理の役割にどのようにつなげていくか、ということが今問われている。
第一に、開発問題と人道的介入は、ポスト・ポスト冷戦期における安保理の役割の中で中心的なものになってくると思われる。安保理が人権や人道を掲げて主権国家内の問題に介入することに正面から反対する声はようやくなくなったが、それではどうやってこれらの問題に対処していくのか、という制度論はまだまだ熟していない。その典型例がダルフールだろう。一昔前であれば国連が介入することさえまかりならなかったが、今年8月に採択された決議案では、部分的に国連憲章第7章を発動させ、場合によってはPKO部隊が武力を行使することさえ許可されている。しかし問題は、このPKO部隊をどこから集めるのか、ということである。また、スーダン政府の合意がない場合でもPKOを展開できるのかどうかについては、安保理の中でも意見が分かれている。ロシア、中国、そしてスーダン政府を後押しするアラブ諸国は反対しているが、アメリカ、ヨーロッパ、ラテンアメリカ諸国は、人権侵害が著しい場合はやむをえないという立場を取っている。それでは日本はどうかというと、日本ではこの問題は全く理解も議論もされていない。
他に安保理が抱えている人道的問題としてはミャンマーが挙げられる。今月も国連政治局長がミャンマーを訪問することになっているが、ミャンマーへの対応がダルフールよりも進んでいるのは、虐殺という形で重大な人権侵害が顕在化する前に国連が介入することができるかという点だろう。また、ジンバブエに対しても、予防的に人道的介入を行うための道筋を作ろうと、アメリカ、イギリスが必死になっている。他方で、これを防ごうとしている国もある。ここでも、日本はその両者の間で右往左往しているだけだ。
第二に、イラク戦争以後の課題として、大国の利害が直接絡む戦争を安保理が防ぐことができるのかどうか、という点がある。これは9.11テロが起こって以来、ずっと問われ続けていることである。唯一の超大国であるアメリカといえども、安保理を通さずして武力を行使してはいけないのか。それとも、国連の枠外で有志連合によって武力が行使されてもよく、国連はそれを容認せざるをえない程度の存在にとどまるべきなのか。イラクへの復興支援をどう行っていくかも含めて、今それが問われている。
皮肉なことに、日本は北朝鮮の核・ミサイル問題が起きて初めて、国連を安全保障上のツールとして使わざるをえなくなった。これまでは右派・左派共に国連を「平和の象徴」として担ぎ上げていればよかったが、北朝鮮の核問題以来、綺麗ごとで国連を持ち上げているだけではすまなくなってきた。戦後初めて、国連を集団安全保障体制というその本来の姿として見ざるをえなくなったのだ。日本も、国連、特に安保理の内部で何が起こっているのかに注目しなければならない状況に置かれている。
担当:大槻、大仲


