第117回 藤原 広人さん 国連政務局事実調査委員会

プロフィール
藤原広人(ふじわら・ひろと):1966年北海道室蘭市生まれ。国際基督教大学(ICU)教養学部社会科学科卒。日本長期信用銀行勤務を経て、国際基督教大学大学院行政学研究科およびオランダ・ライデン大学法学部大学院修了(国際公法専攻)。UNHCR ウガンダオフィスにて難民保護官補として勤務(1993‐1995年)後、1995年より旧ユーゴスラビア刑事裁判所(ICTY)検察局に入り、旧ユーゴ諸国における戦争犯罪・ジェノサイド等国際犯罪の証拠分析に従事。現在、国連政務局事実調査委員会に分析官として勤務。ベルギー・ルーバン大学法学部博士候補。
Q. 高校生の頃はどのような夢をお持ちでしたか。
全寮制の高校に通い、いつも寮の友達と将来何になりたいか話していました。その当時、ジャーナリストと国連職員に憧れていたので、思い切って当時NHKにおられた平野次郎さんと国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の東京事務所にそれぞれ手紙を書きました。平野さんには「自分はジャーナリストになりたくて海外で取材がしたい。平野次郎さんの出身校である国際基督教大学(ICU)に入学したい」と書いたんです。
そうしたらご本人から長い手書きのお返事を頂き、「ICUに入るのはすごく良いと思います。できれば学部のうちに留学することをお勧めします」とアドバイスを頂きました。一方、UNHCRには「社会学を勉強したいけれどUNHCRでは役に立ちますか」と質問したのを覚えています。こちらもお返事を頂き、「社会学も良いですが、それよりも難民のキャンプ設営に必要な物資を運ぶロジスティックスや保健衛生関連の専門の方がポストも多いのでお勧めします」と書かれてありました。でも自分は文系だったので、迷った末にICUで社会学を専攻することにしました。
国連の存在をはじめて意識したのは、小学6年から2年間家族でエジプトに滞在していた際、家の近くにユニセフの事務所があり、青い国連旗を見てこれは何だろうと思った頃に遡りますが、国連職員に具体的に憧れたきっかけは、高校時代に地元の書店で偶然手にして衝撃を受けた『チュイ・ポン-助けて』(三留理男著)というカンボジア難民の写真集の中に、難民キャンプで働く国連職員が出てきて強い印象を持ったことや、同じ頃に手にした『国連ビルの窓から』(明石康著)や『国連に生きる・日本人国連職員の体験記』(世界の動き社)といった本に大きな影響を受けたことです。
Q. 学部卒業から社会人生活を経て大学院に戻られた経緯をお聞かせください。
大学卒業後、89年に日本長期信用銀行に入行したのですが、当時は日本経済がバブル期にありました。そうしたなか、高校時代に思い描いていた夢を思い出し一年で退職。国連に行くには国際法を専攻するのが一番良いと思い、大学院に入り横田洋三先生の下で学びました。紆余曲折はありましたが、結局は国連を目指していたのだと思います。
Q. 国連で勤務されるきっかけを教えてください。
大学院在学中に半年間休学してエチオピアに行き、NGOで緊急援助の仕事にかかわったのですが、そのときの経験が非常に魅力的で、自分は現場に合っていると感じました。しかしそのNGOの資金が続かなくなり、プロジェクトが終わってしまいました。そのとき、以前一時帰国したときに受験していたJPOから合格通知が届いて、難民保護官補としてUNHCRのウガンダ・カンパラ事務所に派遣されたのが始まりです。
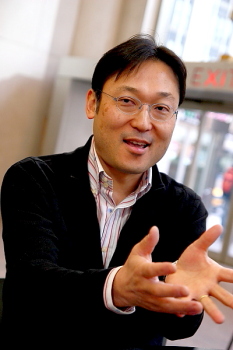
主な仕事は、難民認定の申請をする人たちの審査や、ウガンダ北部に10数万人いるといわれるスーダン難民の保護でした。例えば、ロード・レジスタンス・アーミーと呼ばれる集団やスーダンの反政府ゲリラが、難民キャンプに侵入して夜な夜な難民を拉致したり兵士として強制的に徴用したりしていたのですが、ウガンダの治安当局と掛け合い女性や子どもたちを安全な場所に隔離するためのシステムをつくりました。また、難民が不法入国でウガンダ政府に逮捕された場合には自ら出廷して身元引受人となり、釈放されるための交渉にあたることも重要な仕事でした。
UNHCRは国連機関の中でも特に現場に近く、「人との接触」が難民保護官補の仕事の重要な要素です。その中でもソマリア難民は特に思い出深いですね。彼らは基本的に国境を越えて方々を放浪する遊牧民なので、ソマリアからウガンダまで1500キロ以上の道のりを自分の庭のような感じで軽く移動します。実は、あの界隈で彼らが多く就いているソマリア系の職業は長距離トラックの運転手なんです。だから1か月に1度難民登録更新のために事務所に来なくてはならないのに、ソマリア難民の場合半年から1年間ほどいなくなってしまいます。
でも、あるときカンパラの公立図書館から本を借りたまま1年以上返却していない難民がおり、UNHCRの事務所にペナルティーの手紙が送られてきたことがありました。真っ向から「図書館から督促状が来ているので出頭してくれ」と言っても来てくれないので、どうしたかというと、事務所の待合室にあるヨーロッパ等への第三国定住をするための面接日を通知する掲示板に、何も書かずに彼の名前だけ貼っておいたんです。すると2日後に彼は嬉々として現れ、「私のインタビューはいつですか」と尋ねてきました(笑)。本人曰くソマリアに里帰りしていたらしいのですが、携帯電話も高速道路も存在しない地域で、2日で1500キロの距離を超え彼のところまで情報が届いた伝達網と、その距離を本人が移動したということが信じられませんでした。
その他、事務所で死んだふりをする難民もいました(笑)。1日中廊下で寝ているので、彼の上をまたいで部屋に入って仕事をしていました。事務所が閉まる時間になっても寝ており、「帰ってくれ」と言っても帰らず、仕方がないから彼を自分の車に乗せて、住処であるという捨てられた古い電車の車両まで連れて行きました。「もう二度と来るなよ」と言っても「絶対行ってやる」と言われ、翌日職場に行ったらまた彼が来ていたということもありました(笑)。
笑い話に聞こえますが、この難民にしても誰かに自分がここにいることを認めてもらいたくて他人の注意を引きたかったのだと思います。パスポートや国籍をはく奪され、自分が何者であるのか確認するすべを喪失してしまった人たちにとって、UNHCRは人間としての尊厳を回復する仲立ちをする役割があることを実感しました。
Q. 旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所(ICTY)にはどのような経緯で移られたのですか。
実際にUNHCRでの勤務環境は苛酷で、任期中に肝炎にかかり日本へ約3か月間帰国しました。ウガンダにはその後戻りましたが、健康が回復するまで比較的勤務環境の良いところに移れないかと思い、ジュネーブの日本政府代表部国際機関人事センターを訪ねたところ、当時人事院から出向していた方から、「ハーグで旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所(ICTY)が立ち上がり、現在職員を募集しているので受けてみないか」というお話を頂きました。
早速その場で電話をかけアポを取り、翌日ハーグに飛んでICTYを訪れたのですが、当時は保険会社のごく一部を間借りし、ちょうど事務所を立ち上げようとする真最中でした。捜査部長のところへ行くと、分析官と捜査官の2つポストがあるがどちらが良いかと聞かれ、その場で検察の分析官を希望しました。現在の採用システムでは考えられないことですが、その後面接に進み数か月後にオファーを頂きました。

当初は2年間のつもりで健康が回復したらアフリカに戻る予定でいましたが、ICTYの仕事も面白くなり、オランダで家族もできて結局14年が過ぎました。その面白さとは、ひとつの組織が立ち上がっていく過程に携われたことと、前例のない国際裁判を「人との接触」を通じて創っていく作業に感じた大きな魅力です。例えば、頻繁に現地へ飛び大統領から字も読めない年老いた村人、被害者に至るまで様々な人たちと会ううちに、彼らにとっての我々の仕事の意義を感じるようになりました。
刑事裁判で被害者に出廷してもらい、公の場で自分の受けた経験を話してもらうことは非常に難しい。もう一度犯人に会い、二次的なトラウマを持つ人もいます。ただ、稀にですが、犯人と対峙することでトラウマを乗り越え、喪失した人生をもう一度歩き始める人たちを目撃する瞬間があります。その現場に立ち会うと、自分のやっている仕事にも意味があるのではないかと思うようになりました。「彼らの嘆きや悲しみを誰かが代弁しなくてはならない」と。また、悲惨な経験をしている人たちが誰かに話すことで苦悩を乗り越えられることもあるのだということにも気付きました。僕はいつも仕事で出会った人々を通して、自分の仕事の意義を認識してきたように思います。この仕事には、ドラマチックだけどヒューマンなものがあります。
Q. 今なさっているお仕事はどのようなことですか。
現在は、ICTYからニューヨークの国連政務局に移り、ある国で起きた襲撃事件の調査をしています。事件当時の状況や事件の背景を、残された証拠を検証して少しでも解明することが任務です。ただ、現地の治安が悪く出張したくても許可が下りにくい状況にあり、最近はなかなかニューヨークから出られなくなっています。
Q. どんなときに仕事で悩みますか。
具体的な仕事のレベルで言うと、被害者などの当事者にインタビューしているときに、必要な証言を引き出したいのに出てこないときです。こちらの質問の向け方が悪いのか、その人の信頼を得られず心をまったく開いてくれないときに、自分の無力さをすごく感じます。特に、その人の証言内容をこちらが事前に予測できていて、記録として残したいのに出てこない場合が辛いですね。
もう少し大きなレベルだと、政治的な横槍が入り、捜査を止められたり、違う方向に向かわされる圧力がかかっていると感じたりするときです。我々がやろうとしている真実の追究が政治的な介入により明らかに阻害されるときですね。
Q. 将来はどのような分野でキャリアアップされていくおつもりでしょうか。
ニューヨークにもう少し長く居ることになるかもしれないし、古巣のハーグに戻るかもしれない。カンボジアや東チモールに行くかもしれないといった感じで、将来どうなるのか現時点ではまったくわかりませんが、キャリアアップよりも、与えられた場所で、これまで培ってきた専門や経験を生かした仕事を続けていきたいと思っています。

Q. 国連で働く魅力は何でしょうか。
国連にはひとつの大きな目的があって、それに向かって、発想や言葉の違う多国籍の人たちが力を合わせて創り上げていくという醍醐味があります。また、国連ならではともいえる、大きなプロジェクトにかかわることができることも魅力です。例えば、戦争犯罪裁判のみならず、紛争後の社会復興の促進や当事者間の和解までを視野にいれたプロジェクトは、国連ならではのものではないでしょうか。戦争犯罪裁判にしても、特定の国が設立する裁判はどうしても政治的な偏りがありますが、国連がやるからこそ中立性がある程度確保されると思います。
Q. これまでで一番思い出に残った仕事は何ですか。
あるとき、ボスニアの強制収容所の元所長にインタビューする機会がありました。彼らの精神的構造では、自分が何百人、何千人殺そうが良心の呵責を感じません。家畜を殺すような感覚で、効率よく人を殺せることが組織での出世に繋がると言います。その部分だけを聞いていると、こちらがおかしくなりそうな話ですが、突然彼のものすごく人間的な一面を見ることがありました。
それは、自分の親友を収容所に送らなければならなかった話のときです。彼の権限で親友を釈放できたはずなのに、それをせずに放置したため別の収容所に移送されて死んでしまった、と号泣し始めたのです。「では、あなたが死に追いやった何百人という人たちはどうなるのか」と質問を向けたのですが、彼の中では全く重ならない2つの精神構造が存在していたのです。
泣いている彼の姿は、ほとばしる人間的な部分である反面、何百人を殺したという事実に良心の呵責を感じない部分も現実であって、何か強い別の価値規範が彼を支配しているように感じました。「民族の生存のためには自分のやっていることが必要なんだ」という、戦争を正当化してゆく過程で喧伝されたイデオロギーのようなものが、彼が人間として本来備えている価値規範や良心の呵責を感じる部分を押さえつけ、これを感じさせないようにしているように思えました。
Q. 博士課程ではどのようなことを研究されていますか。
今はベルギーのルーバン大学で博士課程に所属していますが、自分の仕事を客観的に見る助けになっています。具体的には、最近の国際法の発展の過程でICTYが果たしてきた役割を学問的に考察すると同時に、紛争後の社会において「共通の記憶」(紛争地で何が起きたのか)が形成されていく中で、国際刑事裁判が果たす役割についても研究しています。国際刑事裁判には国際犯罪の責任者を捕まえて処罰するという一義的な機能がありますが、ある意味それ以上に重要なのは、「紛争地で何が起き、誰がどこで何を行い、どのような背景でなぜそれが起きたのか」という一定の説明を与えることです。
情報が錯綜して混沌とした紛争後の社会状況の中では、みんな何が起きたか分からないのです。でも、分からないなかでも国際刑事裁判が果たすべき役割は、公に「これはこういうことだったんだよ」と示すことです。この説明を受け入れ側の社会が否定し、受け付けないことも可能ですが、これから復興しようとする社会がこうした説明を一つの枠組みとして捉え、これと向き合い格闘することが重要です。それがないと先に進めません。先というのは究極的には被害者と加害者の和解を意味しますが、和解プロセスそのものが可能になるための前提として、まずは、紛争地で何が起きたのかということについて共通する認識が必要です。そのための基盤を提示することが国際刑事裁判のひとつの重要な機能として与えられているのです。
Q. 日本がこの分野でどのように貢献できると思いますか。
日本は、「刑事裁判で悪い者を捕まえ処罰する」という懲罰的なアプローチだけではなく、被害者と加害者が向き合うことのできる環境を作り、共に国を再興してゆく過程において、多大な貢献ができると思います。日本人の長所や素晴らしい部分を生かせる分野として、例えば、まだ立ち上がったばかりの国際刑事裁判所(ICC)の被害者信託基金(The Trust Fund for Victims)への貢献があげられます。同基金は、ICCが扱う紛争後社会の被害者を対象に、彼らが瓦礫の中から再出発し、再びひとり立ちできるための支援を行うことを目的としていますが、具体的に基金をどのように運用するかについて、固まったルールはまだ出来上がっていません。
被害者一人ひとりに補償金の形で金銭を支払うというのもひとつの方法ですが、その場合、補償対象となる被害者をどの範囲で確定するのかとか、補償の結果、補償対象となった被害者とその他の周辺住民との経済格差が拡大するのではないか、など種々の問題が想定されます。しかし同基金は被害者救済の方法を個人への金銭的補償に限定しているわけではありません。被害を受けた地域全体が共同体として再興するために、日本が長年培ってきた開発援助のノウハウや豊かな経験を生かしたアイディアを提供することができると思います。
紛争後社会が再興してゆく過程は通常長いプロセスで、その意味で息の長い援助が必要です。息の長い援助を誠実に続けることが得意な点も、日本人の持つ素晴らしい特質のひとつであると思います。

Q. グローバルイシューに取り組む人たちにメッセージをお願いします。
僕は高校生のころから国連に入りたくてこれまで歩んできました。田舎の高校生だった自分が憧れの職業に就いている人たちに手紙を書き、返事までいただいて大喜びしていました。今振り返ってみると、国連に入るのを目標にしてそのために準備したことは良かったと思います。確かに、冷めた見方をすれば、国連だって単なるひとつの職業に過ぎないと言えるかもしれません。でも僕にとって国連での仕事は数ある仕事のひとつではなく、特別な意味を持った職業(英語でいう”calling”)であると感じています。
もちろん、最初は戦争犯罪を仕事にするつもりはありませんでしたが、国連に入りたい気持ちを温め続け、国連に入りたくて大学を選び、専攻を選び、銀行に入ってもまた戻ってきて国連を目指し、紆余曲折を経てここまで辿り着きました。
国連は完璧な組織ではないし、外からの期待と実際にできることの落差に挫折感を強く感じることもあります。でも、「にもかかわらず」だと思うんです。様々な欠点があるにもかかわらず、辛いなと思う時に国連に居続けることの意味とこの仕事のやりがいを感じる。そんな職場ってあまりないと思います。
国連理想論に聞こえるかもしれませんが、国連に入ることは立身出世のための手段じゃない。お金や権力が目的であれば、むしろ入らないほうがいい。国連の仕事の本質は「他者への奉仕」であり、紛争の原因を除去するだけでなく、紛争などの人為的災害や、自然災害によって打ちひしがれた人々が、再び立ち上がり、夢を持ってチャレンジすることができるよう手助けするところにあると思います。言ってしまえば、このような青くさい理想がそのまま有効性を持っているところです。
僕がこれまで国連の職場で出会った同僚たちの中にも、本当にこうした理想を生きている、謙虚で尊敬できる人々が何人かいました。例えばアメリカで最高のロースクールのひとつを出たあと、著名な事件をいくつか手がけ、そのまま弁護士として働けば大きな収入を簡単に手にすることができるにもかかわらず、40歳をすぎてからインターンとしてICTYに入り直し現在まで一職員として働いている人や、ドイツの大学教授国家資格を持ち、何十本もの学術論文を発表している研究者が、やはりICTYの最もジュニアのレベルから入ってこつこつと大切な仕事をしている例などです。
最後に、今あげた例も含めて、国連への就職の道は幾通りもあり、それぞれケースバイケースで確実なノウハウが存在しないのが難点ともいえますが、それは利点でもあります。様々な年齢やキャリアの段階にある人々が、それぞれ異なった方法でチャレンジできる点です。国連には「新卒採用」という言葉がないと同時に「中途採用」という言葉も存在しません。国連職員は、ある意味で全員が中途採用だからです。実は、国連に至る道の多様性そのものが国連らしさ(ひいては国連が反映する世界の多様性)なのかもしれません。熱くて大きな志を持った日本人に、これからもどんどん国連に入ってきて欲しいです。
2009年11月7日 ニューヨーク
聞き手:宇那木智子
写真:田瀬和夫
プロジェクト・マネージャ:鹿島理紗
ウェブ掲載:渡辺哲也


