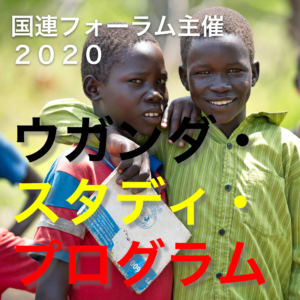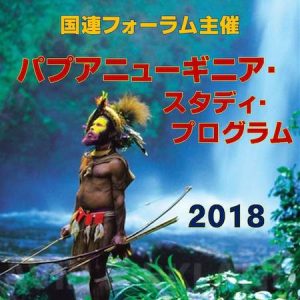国連フォーラムでは、勉強会や投稿エッセイなどの知的意見交換の場の他に、国連の現場での活動を実際に訪問するスタディ・プログラムを2010年より主催しています。
2010年の第一回目は東ティモールへのツアーを敢行し、2011年はタイのメーホンソーン県、2012年はカンボジア、2013年はモンゴル、2014年はミャンマー、2015年はスリランカ、2016年はネパール、2017年はルワンダ、2018年はパプアニューギニア、2019年はヨルダン、2020年はウガンダ、2024年はコロンビアを対象としてプログラムを実施し、2025年はバングラデシュへ渡航します。
SNS

2025年:バングラデシュ・スタディ・プログラム(BSP)
2025年のスタディ・プログラムは、バングラデシュを対象とし、「バングラデシュの今を歩く~平和・人権・開発の交差点で考えるこれからの国際協力~」を中心的なテーマとして実施します。かつて最貧国の一つとされたこの国は近年目覚ましい経済成長を遂げる一方、格差や貧困、児童労働、気候変動による移住といった複雑な課題が依然として存在します。さらに、支援を受ける立場であると同時に、ロヒンギャ難民の受け入れなど支援を行う側としても重要な役割を果たしてきたバングラデシュ。国連の三本柱である平和・人権・開発が揺らぐ今、この国を舞台に、交錯する課題のただなかで「これからの国際協力のあり方」を分野を越えて深く探究していきます。

2024年:コロンビア・スタディ・プログラム(ColSP)
2024年のスタディ・プログラムは、コロンビアを対象とし、「南米コロンビアで考える、レジリエンスと平和構築〜地球との共生・地球での共生への葛藤と希望とは?〜」を中心的なテーマとして実施します。世界中が大きく揺らいだパンデミックを経て、約3年ぶりの開催となるスタディ・プログラム(SP)。2024年度に向かうのは、SP史上初の南米コロンビア。50年以上続いた紛争を経て、現代はベネズエラ難民や国内避難民、経済移民の移動や経済格差などの「人の課題」、さらに「生態系のゆりかご」という異名の通り生物多様性保全や気候変動による自然災害など「自然の課題」にも取り組んでいます。平和と発展のために不条理に抗いながら奮闘する人々の姿勢から、未来に描く「地球との共生と地球での共生」のあるべき姿を徹底的に模索します。
2020年:ウガンダ・スタディ・プログラム(USP)
2020年度のスタディ・プログラムは、TICAD7から1年ということもありアフリカ、その中でも「ウガンダ」を対象とします。長期間続いた国内紛争からの復興、周辺国からの難民受入、ジェンダー課題や子どもの保護、貧困削減、豊かな自然と社会・経済開発のバランスなど多様な課題を抱えています。これらの課題について、2015年に国連総会で採択されてちょうど5年となるSDGsと、そのキーワードである5つのP(Peace, People, Planet, Prosperity, Partnership)を手掛かりにしながら、1年間のプログラムの中で考えていきたいと思います。
2019年:ヨルダン・スタディ・プログラム(JSP)
2019年のスタディ・プログラムは、ヨルダンを対象とし、「激動する中東の中心で紛争と共存、世界の平和を考える~持続可能な社会を目指す新しい難民政策のあり方とは~」を中心的なテーマとして実施します。
2018年:パプア・ニューギニア・スタディ・プログラム(PSP)
2018年のスタディ・プログラムは、パプアニューギニアを対象として実施します。日本からそこまで遠くないにもかかわらず、あまり知られていない国のひとつかもしれません。「島嶼国パプアニューギニアから考える「国際協力」の意義・役割とは?~自然と人間の「分断」と「共生」~」を中心的なテーマとして、紛争からの復興や開発課題という従来のスタディ・プログラムが中心としてきた議題に加えて、気候変動や環境問題にもアプローチする予定です。

2017年:ルワンダ・スタディ・プログラム(RSP)
2017年2月15日にルワンダ・スタディ・プログラムの実施を発表し、参加者募集を開始しました(3月12日まで)。

2016年:ネパール・スタディ・プログラム(NSP)
2016年はネパールを対象国として学びました。もともとカースト制度などで社会の中に大きな格差や貧困問題があるときに大きな自然災害が起こるとどうなるのか、国際社会がそうした国や地域に対して出来ることとできないことは何か、日本の東日本大震災との比較ではどのようなことが言えるのかなど、多角的な学びを得ました。

2015年:スリランカ・スタディ・プログラム(SSP)
2015年は9月にスリランカへ渡航しました。テーマは「紛争後の平和構築と持続可能な社会づくり」。国連を中心にNGO、二国間ドナー、営利企業等様々なアクターによって実施されているプロジェクトの実例を視察し、学んだことを参加者同士で議論することを通じて、国連及び国際社会がどのように発展途上国の開発支援に関与していくべきか、本来非常に幅の広い概念である「平和構築」の概念とポスト2015年開発目標の議論の中で注目されている「持続性」をテーマにしながら考えました。

2014年:ミャンマー・スタディ・プログラム(MySP)
2014年は11月にミャンマーへ渡航しました。急速な民主化と経済成長により国が大きく変化しようとしているこの国が抱える諸課題について、それらに対する国連や国際社会の関わり方について学んできました。
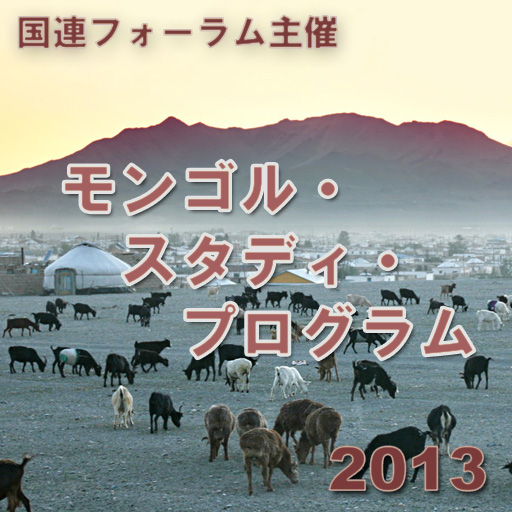
2013年:モンゴル・スタディ・プログラム(MSP)
2013年は8月にモンゴルに渡航しました。急激な経済成長下におけるモンゴルの諸課題(コミュニティ開発、自然災害と直面する農牧業、都市・環境問題など)に取り組むモンゴル政府や国際機関等の活動現場を訪問しました。

2012年:カンボジア・スタディ・プログラム(CSP)
2012年については、11月の後半にカンボジアを訪れ、紛争後の社会がどのように復興しているか、国連や国際社会はそのように紛争後の社会を支援しているのかを学びました。カンボジア特別法廷、ナカタアツヒト村、かものはしプロジェクトによる人身取引対策事業、ユネスコの世界遺産候補となっている遺跡、FAOの食料安全確保事業などを訪ねました。

2011年:タイ・スタディ・プログラム(TSP)
2011年には、「みんなでつくる」を原則に、23名の参加者がタイのメーホンソーンで実施されている国連の人間の安全保障基金事業を訪ねました。川を四輪駆動で渡るしか到達手段のない農村など、タイの先住民が直面する課題に対応しようとする国連の取り組みについて学びました。事前に関東と関西で3回の勉強会、事後にも関東と関西で報告会を行い、また報告書、DVD映像などの記録も作成しました。

2010年:東ティモール・スタディ・ツアー
2010年に行われた「東ティモール・スタディ・ツアー」は、9月5日(土)~11日(土)の6泊7日 で、東ティモールの首都、ディリ集合、ディリ解散で行われました。催行人数は40名とかなり大規模なもので、UNMITのブリーフィング、UNDPやUNICEFの事業視察などを行いました。事後には有志による勉強会が継続的に行われました。
スタディ・プログラム|ご提供いただく情報の取り扱いについて
2025年3月29日版
スタディ・プログラム(以下SP)では、国連フォーラムの基本原則に則り、ご提供いただく情報について以下の基本的事項を定めています。
- 情報は、SPタスクフォース(以下TF)において管理し、最終責任者は国連フォーラム代表理事とします。
- 情報は、SPの目的・活動に必要な限度を超えて利用されることはありません。特に、メーリングリストやウェブ上等にて統計的なデータを公表する場合を除いては、いかなる場合も、個人の意思に反してTF外部に情報提供することはありません。
- 情報の修正・更新・削除などの依頼に対する速やかな対応に努めます。