![]()
CDM���x��ʂ��������\���ւ̓��̂�
�|�C���h�l�V�A���P�[�X�Ƃ��ā|

�@
���[�W���i���e�N�j�J���X�y�V�����X�g�i�C��ϓ��S���j
���A�J���v��E�A�W�A�����m�n�掖�����i�o���R�N�j
�{���M���i�݂₮�����������j����
�����F���s���܂�B�~�V�K����w�A�i�[�o�[�Z�i���w�m�E���R�������j�A�I�b�N�X�t�H�[�h��w�i�������w�j�A�t���C�u���N��w�i�h�C�c�E�������w�j�A�V�J�S��w�i��������C�m�j���o�āA���A��w�ɋΖ��B���̌㐢�E��s�E�����J�����[�j���O�Z���^�[�Ζ����o�āA�Q�O�O�U�N�V����� UNDP�C���h�l�V�A�������ɂċC��ϓ��S���̃v���O�����I�t�B�T�[�Ƃ��ċΖ���A�Q�O�O�W�N�P����茻�E�B
�P�D�͂��߂�
�Q�D�w�i
�R�D���_
�S�D����
�T�D��
�U�D�Ō��
�V�����E��Ɉڂ������肾���A���������Ŏ��̓A�W�A�����m�n���ΏۂɋC��ϓ��̊ɘa�iMitigation�j�ƃJ�[�{���t�@�C�i���X�Ɋւ���Ɩ���S�����Ă���B�n�����t�@�V���e�B�iGEF�j�A�����ăN���[���J�����J�j�Y���iCDM�j�̃v���W�F�N�g�J���y�ъǗ��Ƃ������e�ł���B�A�W�A�ɂ͒����ƃC���h���܂߁A���E�̒��ł��L���̌o�ϐ����𑱂��Ă���n��ł���A�܂����̒S������C��ϓ��Ƃ����g�s�b�N���猩�Ă����E�̒��ł����ɏd�v�Ȓn��ł���Ƃ������Ƃ͓��ɋ�������K�v���Ȃ��Ǝv���B����͎������܂łɋΖ����Ă����C���h�l�V�A���ɂƂ�ACDM�Ƃ������x��ʂ��āA�����ɂ���Ύ����\�Ȕ��W�Ɍ������Ă�����̂��Ƃ����_�����Ă��������Ǝv���B
�ŋ߂̋C��ϓ��Ɋւ��鐢�E�̊S�̍��܂�͂��̐��N�A�����ē��ɂQ�O�O�V�N�̎n�߂��납��w�����I�ɑ����n�߂���������B�܂����܂łɂȂ��p�x�A�����ċK�͂̎��R�ЊQ�̔�������n�܂�A�ڂɌ�����`�ł̋C��̕ϓ��Ƃ������̂����X�����������������ĉ�X�ɔ����Ă������Ƃ���������B�Q�O�O�V�N�͂��̂悤�ȋC�ۂɊւ���j���[�X�����łȂ��A�C��ϓ������͂ޑ��̗l�X�ȏo�������������B�ȒP�ɂQ�O�O�U�N���Ղ����N���܂ł̗�������Ă����ƁF
�@�@�E �Q�O�O�U�N�T���@�A���E�S�A�́u�s�s���Ȑ^���v�̌��J���n�܂�B
�@�@�E�Q�O�O�U�N�P�O���@�g�X�^�[�����r���[�h�����\�����B�j�R���X�E�X�^�[�������E��s�㋉�����ق��܂Ƃ߂��A�C�@��ϓ����y�ڂ��o�ωe���Ɋւ��Ă̕�I�ȕ��i���{��v��ŁiPDF�j�j�ŁA�C��ϓ��̔�Q�͒����ɋy�Ԃ��̂ł��̔�Q�͐r��ł���A������Ƃ邱�Ƃ������I�Ȕ�Q�̋K�͂��l���Ă��o�ϓI�ɗL���ɂȂ�A�ƌ��_�t�������́B
�@�@�E�Q�O�O�V�N�Q���@�u�C��ϓ��Ɋւ��鐭�{�ԃp�l���i�h�o�b�b�j�v�̂U�N�Ԃ�̕������\�����B���̑�S���]�����ł͋C��ϓ��͐l�Ԃ̊����������ł���Ƃ��������\�����������A���s�c�菑��ʂ����������ʃK�X�̍팸�ʂł͖�肪�������Ȃ��A�Ƃ������Ƃ𗠕t������ƂȂ����B
�@�@�E�Q�O�O�V�N���� �C���h�l�V�A���{���C��ϓ��g�g���A��P�R�����c�iCOP13�j�̊J�Â𐳎����肷��B
�@�@�E�Q�O�O�V�N���� �A���S�A�̉f�悪�A�J�f�~�[�܂����
�@�@�E�Q�O�O�V�N�P�O���@�A���S�A��IPCC�Ƌ��Ƀm�[�x�����a�܂����
�@�@�E�Q�O�O�V�N�P�Q���@COP13�J�ÁB188�����̒����͂��߁A���ۋ@�ցANGO�����܂�1���l�ȏオ�Q������Ƃ������܂łɂȂ��K�͂̊J�ÂƂȂ����B
�����C���h�l�V�A�ɕ��C�����̂��Q�O�O�U�N�̂U���ł���A���̂悤�ɕ��C���̂P�N���͂܂��ɋC��ϓ��̐��E�I�ȓ�������������܂��ƂȂ��@��ƂȂ����B�C��ϓ��Ƃ����傫�ȕ���̖��[�ɂ���҂Ƃ��āA���ۂ�COP13�ւ̎Q�����܂߂āA�n���K�͂ł̈ӎ��̕ϊv���N�����Ă���Ƃ������Ƃ������ł����C������B
�C��ϓ��ɂ͓�̑傫�ȕ��삪����B�ɘa�iMitigation�j�A�����ēK���iAdaptation�j�̓�ł���B����̒Ŏ��グ��̂͂��̊ɘa�Ɋւ�����̂ŁA����͉������ʃK�X�iGreenhouse Gas�AGHG�j�̍팸�Ɋւ��A���ړI��GHG�̍팸��A�܂��X�т₻�̂ق��̎�i��GHG�̋z���ʂ�������悤�Ȏ�i���܂߁A���g���̉e�����ŏ����ɗ��߂悤�Ƃ��銈���ł���B���������̊ɘa��̐��ʂƂ����̂͐��\�N�Ƃ������̂����ł���ƌ����Ă�����̂ł���i���Ƃ���GHG�̑唼���߂��_���Y�f�͑�C���ɂP�O�O�N�ȏ㗯�܂邱�Ƃ��w�E����Ă���j�A�����݉�X���ڂɂ��A�̌����Ă���C��ϓ��ɑ��ẮA���������̉�����i�ł͎c�O�Ȃ���Ȃ��B���N�����Ă���C��ϓ��̉e���ɑ��ēK����𑣂������͓��ɔ��W�r�㍑�Ŋ����ł���B���̓K���Ƃ�������́A�ɘa���삪���E�S�̂�Ώۂɂ��Ă���̂ɑ��A�ΏۂƂȂ�n�悪���ꂼ��̍��A�����Ēn��Ɍ��肳�����̂ŁA���E����GHG�r�o��������Ή����i�܂��͂���Ɍ�������Ɓj����Ƃ����A���������ɓ��������r�I���ꂳ�ꂽ���肪����̂ɑ��A�K������Ƃ������̂͂��̓y�n�y�n�A���X�ɂ���������̂�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����̂ł���B
���C��ϓ��̖��̉��ōs���Ă��銈���A�����Ă��̎����K�͈͂��|�I�Ɋɘa����ɔ�₳��Ă���B����͋��s�c�菑���y���A�@�I�S���͂������l�ڕW�̋`�����Ă��镍�����T���i���W���̃O���[�v�j�́A�팸�ڕW�Ɍ������w�͂����̂܂܊ɘa��ƂȂ邩��ł���B�������݂܂łɐ��\���h�����x���ł��̕���ɂ����Ď����������Ă���A���̓����͓��ɓ��Ɋ������𑝂��Ă���B�܂����ɂQ�O�O�W�N�͋��s�c�菑�Ō��������ԁi�Q�O�O�W�|�Q�O�P�Q�j���n�܂�N�ł�����A����ɋC��ϓ��́A�����Ċɘa����Ɋւ��铮���������ɂȂ�N�ƂȂ�ł��낤�B
���̊ɘa��ł��邪�A�@�I�S���͂������l�ڕW�̒B���ɓ�����A�������T���̎������ł�GHG�팸�w�͂ł͎����ł����Ɍ��E������A�Ƃ���������ӂ݁A���s�c�菑�̒��ŏ_��I�[�u�iFlexible Mechanism�j�Ƃ��āA�����ł̍팸�������̍팸�Ƃ��Ĉ������Ƃ̂ł���u���s���J�j�Y���v���F�߂��邱�ƂƂȂ����B���̒��̂ЂƂł���̂�CDM�ł���B����͋��s�c�菑���y���Ă��邪GHG�̍팸�ڕW�������Ȃ����W�r�㍑���z�X�g���Ƃ��A��i�����Z�p�E�����̎x����ʂ��đ����Ŏ�������GHG�r�o�ʂ̍팸���������̍팸�ɏ[�Ă���Ƃ����d�g�݂ł���B����CDM�̊�����ʂ��A�z�X�g���ɂ�����ʏ�̎Y�Ɛ��Y�����̃V�i���I���Ŕr�o�����ʂƔ�r���č팸���ꂽ�����N���W�b�g�Ƃ����`�ŔF�肷��A�Ƃ������̂ł���B
�ɘa����̂ЂƂ̑傫�Ȏ��g�݂Ƃ��Ĕ�����������CDM�Ƃ������x�ł��邪�A���E��CDM�v���W�F�N�g�̑S�����̂Q�������E�̓K������̎x���̂��߂ɍ����u�K������iAdaptation Fund�j�v�ւ̎������Ƃ��Ď�舵���邱�Ƃ����܂��Ă���B
����CDM�ł��邪�A���Ԋ�Ƃ̖��������ɋ����BCDM���̂��͖̂��Ԋ�Ƃ̎Q�����`���t���Ă���킯�ł͂Ȃ����A��Ƃ̐ϋɓI�ȎQ�������₷���A�Ƃ����_������B���̗��R�̈�ɋ��s���J�j�Y������߂�A�r�o������iEmission Trading�j�Ƃ������x������B����͕������T���̎�X�̊�����ʂ��Ĕ��������N���W�b�g�ɒl�i��t���A���̋��Z���i�̂悤�Ɏ���ł���悤�ɂ��鎎�ł���A�N���W�b�g�̔����l�i�͎s�ꌴ���̌��Ɍ��肳��A�K��̒l�i�Ƃ������̂͂Ȃ��A�����Ɉ��������̃N���W�b�g����ɓ���A��������̂��A�Ƃ�����{�I�s�ꌴ����������Ă���B
�A�����J���������E�̐�i���̂܂��ɂقڂ��ׂĂ����s�c�菑���y���Ă���A�����̍��X�̐��{�̈ӌ������N���W�b�g�̎擾���Ƃ̑��݂́A�����ɂ��̃J�[�{���N���W�b�g���\���ȓ����̑Ώۂɂ��Ȃ肤��A�Ƃ������Ƃ������킯�ŁA���̂��Ƃ����܂łɂȂ����Ԋ�Ƃ̎Q�������҂���Ă��闝�R�ł�����B
�~���j�A���J���ڕW�A�����Đ��E�̕n���������Ɍ������A���Ԋ�Ƃ̎��A�g�lj��I�h�Ȗ����ł͂Ȃ��A�g�⊮�I�ȁh�p�[�g�i�[�Ƃ��Ă̑傫�Ȑ��ݐ��͓������傫�Ȓ��ڂ��W�߂��Ă���A���̒��ł����ɂ���CDM�Ƃ������x�����Ԋ�Ƃɗ^����e���͔��ɋ������̂�����ƌ����Ă���B
�A�W�A�����m�n��ɂ����āACDM�̃v���W�F�N�g�J���̌���͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂ł��낤���B�܂��傫�ȓ����Ƃ��āA�A�W�A�A�����Đ��E�ɂ����Ă��Ƒ���Ԃ������Ȃ̂������ƃC���h�ł���B���̏�Ԃ͓��M�ɒl���A�̍��v���A�A�W�A�S�̂�CDM�̃v���W�F�N�g���łW�S���A�����ė\������Ă���N���W�b�g�̍��v�ʂł��W�T���ƁA���̑唼�����߂�i�}�P�A�}�Q�j�B
�}�P�F�A�W�A�ɂ�����CDM�v���W�F�N�g�̐��̔�r
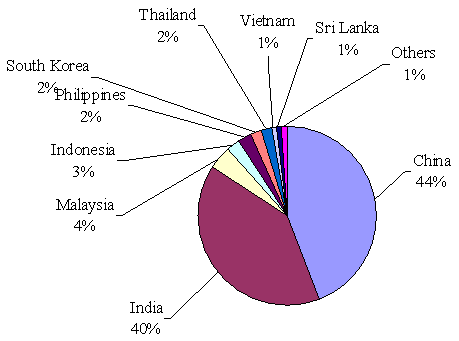
Source: UNEP/RISOE (�Q�O�O�V�N�P�P�����_)
�}�Q�FCDM�v���W�F�N�g��ʂ��ė\������Ă���GHG�r�o�팸�ʂ̃A�W�A�ɂ������r
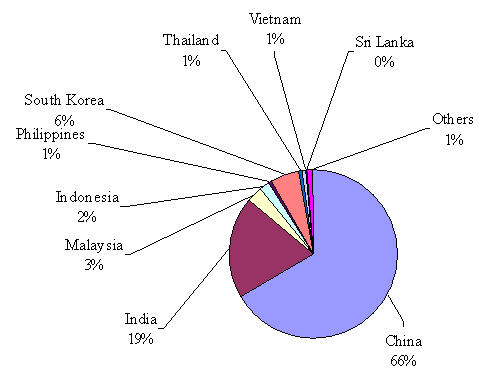
Source: UNEP/RISOE (�Q�O�O�V�N�P�P�����_)
�����CDM�Ƃ������J�j�Y�����̂��̂��������̈�ɋN�����Ă��鏊������B����͋ߑ㉻��������ł��邪�܂��Y�ƁE�Z�p���u�����v�A�܂�GHG���ʂɔr�o���鍑�X����������Ƃ����\�}�ɂȂ��Ă��镔���ł���B�iCDM�Ƃ������x���m�������ȑO�Ɏ����̃C�j�V�A�e�B�u�ŎY�Ƃ��u���ꂢ�Ɂv�ɂ��Ă������W�r�㍑���甽���̐����オ���Ă���̂͂��ꂪ�����ł���B�j������������̂悤��CDM���x�̓����������v���ł͂Ȃ��A���������̐��x�����̗D�掖���Ƃ��A���������Ă��̊J���A���p��簐i���Ă����A�Ƃ��������w�͂̎����ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
���Ă��̂悤�Ȓ����E�C���h�̓Ɛ��Ԃ̒��A�C���h�l�V�A�ł͂ǂ̂悤�ȏ�ԂȂ̂ł��낤���B�C���h�l�V�A�͂P�X�X�S�N�ɍ��A�C��ϓ��g�g�����A�܂��Q�O�O�S�N�x�ɂ͋��s�c�菑���y�����B�����̓K�X��Ζ����͂��߂Ƃ��鎩�R�����A�����Đ��E�ł��L���̔M�щJ�т�����l���Ƌ��ɁA�P���V����̓��X�Ō`������铇���ł�����B���̂��߁A�C���h�l�V�A��GHG�̔r�o�ɔ����Ă̋C��ϓ��̉��Q�ґ��ł���Ɠ����ɁA���ݐi�s�`�ŋC��ϓ��̉e�����_�ѐ��Y�ƁA�����ē��ɉ��u�n�ɂ���n���w�Ɍ����Ă���Ƃ�����Q�ґ��ł�����A�C��ϓ��̓����ɑ傫�ȉe����^����d�v�ȍ��̂ЂƂł���B
�Q�O�O�P�N�ɃC���h�l�V�A���Ȃ����\�������Z�ɂ��ƁA�����͑S���E��CDM�s��ɂ����ĂQ���A�����ɂ��ĂP�D�R�`�R���g����GHG�r�o�팸�̉\��������Ƃ��Ă���B���������̐����͏���LULUCF�i�y�n���p�A�y�n���p�̕ω��y�їыƁj�ƌĂ���ɐX�є��̂�D�Y�n���炭���_���Y�f�̕��o���͊܂܂�Ă��炸�A������܂߂�C���h�l�V�A�͐��E�ő�R�ʂ�GHG�r�o���ƂȂ�Ǝ��Z����Ă���i�A�����J��WRI(���E����������)�̂Q�O�O�O�N���̌v�Z�ɂ��j�B
�ł̓C���h�l�V�A�̌��݂�CDM�̃v���W�F�N�g�̊J���͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă���̂ł��낤���B�܂��Q�O�O�V�N���̎��_�ɂ����āA���łɎ��{��Ԃ̃v���W�F�N�g�A�����ăC���h�l�V�A���{����F�߂��Ă��邪�J���r���A�Ƃ����Q�̃^�C�v�����킹��ƍ��v�łT�Q����B���̐��͂������A�W�A�S�̂Ō���Α����Ȃ����A�C���h�l�V�A�̂Q�O�O�V�N�̂U�����_�ł͂��̔����ɋ߂��Q�V�v���W�F�N�g�ł��������Ƃ��l����Q�O�O�V�N�̌㔼�ł̓����̃v���W�F�N�g�J���̔M�͔��ɍ��܂��Ă��Ă���Ƃ�����B
�T�Q����v���W�F�N�g�̓���́A��Ƀp�[�����̐��Y���̎c�����𗘗p�����v���W�F�N�g����ȃo�C�I�}�X�֘A�̃v���W�F�N�g�A�����ăS�~�����ꂩ��o�郁�^���K�X�̉���Ɋւ���v���W�F�N�g�����̑������߂�i�}�R�j�B
�}�R�F�C���h�l�V�A�ɂ�����CDM�v���W�F�N�g�̎�ށ@�i���v�T�Q�v���W�F�N�g�j
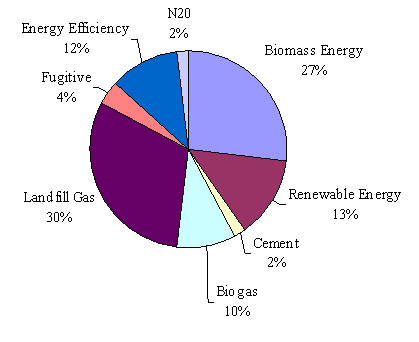
Source: UNEP/RISOE�̃f�[�^�����ɕM�Ҍv�Z
������CDM���x��������x���Ղ��Ă݂�B��������Ƃ��̐��x�̖ړI�͓�̑w�����݂��邱�Ƃ��킩��B��w�͐�i����GHG�r�o�팸�Ƃ����ړI�A�����ĉ��w�͔��W�r�㍑�ɂ�����i�����\�ȁj���W�̎����Ƃ����w�ł���BCDM�Ƃ������x�͂��̊J���A�o�^�A�K�v�Ƃ���镶���A����H���A�����ĔF��Ƃ������Ɍ����Łi�����ĔώG�ȁj�v���Z�X���o�Ď��{����Ă����̂ł��邪�A����炷�ׂĂ͂��̏�w�̖ړI�̐��s�̂��߂̃N�I���e�B�R���g���[���Ƃ��������������Ă���B���E�Ŏ�������N���W�b�g�ނ��߂ɂ͂��̂悤�Ȍ����ȃX�e�b�v��ʂ�Ȃ��ƔF�߂܂����A�Ƃ������̂ł���B�|���Ă��̉��w�̖ړI�ŁA�N���[���J�����J�j�Y���́g�J���h�̉ӏ��ł��邪�A����̓z�X�g���̍ٗʂɔC����Ă���B
CDM�v���W�F�N�g�͂��̂��ׂĂ��z�X�g�����{�ɂ܂��F�肳��Ȃ�������Ȃ��d�g�݂ɂȂ��Ă���A�����ł��̃z�X�g���̈ӌ������f����ăv���W�F�N�g���I������邱�ƂɂȂ�B�C���h�l�V�A���{�����̎�̑I���Ɏg����Ƃ��āA�g�����\�ȊJ�������юw�W�h�iSustainable
Development Criteria and Indicators�j�Ƃ������̂�K�p���A�o�ρA�Љ�A���A�����ċZ�p�ړ]�Ƃ����S�̊ϓ_����v���W�F�N�g�����肷��Ƃ����V�X�e���Ƃ��Ă���B
���������̂悤�Ȋ��w�W�����ۂ̎����\�ȊJ���Ɍ����Č��ʂ��オ���Ă���̂��Ƃ����ƁA�ǂ��������ł��Ȃ��悤�Ɏv����B
�܂��o�ϓI�ȑ��ʂ̂ЂƂ̌ٗp�̑��i�A�Ƃ����ʂ����Ă݂�B��N�̔N�����_�ŃC���h�l�V�A�ɂē����Ă��鍇�v�T�Q�̃v���W�F�N�g�̂����ACDM�̃v���W�F�N�g��ʂ������ڌٗp�ł͎��ɂV�R�����̃v���W�F�N�g�ɂ����Čٗp���܂������Ȃ����A�������͂P�O�l�ȉ��Ƃ����K�͂ɂƂǂ܂��Ă���i�}�S�j�B�T�O�l�ȉ��̌ٗp�ƂȂ�Ǝ��ɂX�Q���ƂȂ�A�v���W�F�N�g�������̒n���R�~���j�e�B�ɋy�ڂ��ٗp�̑��i�Ƃ����ʂ��炷��قƂ�ǂ��̌��ʂ������Ă��Ȃ��A�Ƃ����̂��킩��B
�}�S�F�@�C���h�l�V�A��CDM�v���W�F�N�g��ʂ������ڌٗp�̏�ԁ@�i�P�ʁF�l���j
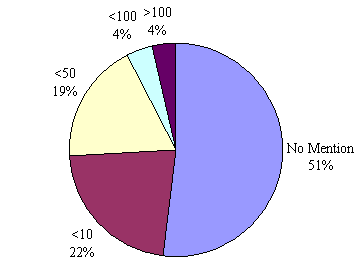
Source: PDD�̏������ɕM�Ҍv�Z
�Љ�I�ȑ��ʂł����A�X�e�[�N�z���_�[�Ƃ̘A�g�A�Ƃ������ʂł݂Ă��A�Ⴆ�X�e�[�N�z���_�[�Ƃ̉����ȏ㎝�����A�Ƃ����v���W�F�N�g�͂P�P�� �ɂƂǂ܂�A�Љ�I�ȃR���Z���T�X�������Ă���̂��A�������͎Љ�I�ȃx�l�t�B�b�g�����i����Ă���̂��A�Ƃ����ʂŋ^�╄��������Ȃ��B
���̖ʂł��A����͏�L�̐��{���w�肵�Ă�������юw�W�̍�����ɋN������Ƃ��낪�傫�����A�����R���v���C�A���X�ȏ�̊������قڂ݂��Ȃ��B�����E�n�����{����߂�K��ȏ�̊��������Ă���CDM�v���W�F�N�g�͂O�D�S��1�ɂƂǂ܂�A�R���v���C�A���X�ȏ�̊������قڊF���A�Ƃ����������Ă���B
�Ō��CDM�̈�Ԃ킩��₷���A�����ĉʂ����₷���Ǝv����v�f�ł���Z�p�ړ]�̑��ʂł��邪�A�ŐV�́u�Z�p�v�͎g���Ă���̂ł��邪�A���ꂪ�ʂ����āu�ړ]�v����Ă���̂��Ƃ����Ƃ����ł��Ȃ��A�n���̊�Ƃ⎩���̂ւ̐ϋɓI�ȋZ�p�̈ړ]���s���Ă���ƌ�����v���W�F�N�g�͂S�P���i�Q�O�O�V�N�U�����_�BPDD�̋L�q�����ɕM�Ҍv�Z�B�j�ɂƂǂ܂�A���̂R�̊�ɔ�ׂ�ΑP�킵�Ă͂�����̂́A���̑��ʂł��u�����\�ȊJ���v�Ɍ��������ʂ����݂�CDM�v���W�F�N�g��ʂ��ăC���h�l�V�A�ɂĎ������Ă���Ƃ͌����ɂ����̂������ł���B
����͂܂������̕M�҂̐����ƂȂ邪�A���̂悤�ȏ�Ԃ��C���h�l�V�A�������̂ł���Ƃ͂������ꂸ�A�A�W�A�̂ق��̍��ł����̂悤�ȏł͂Ȃ����Ǝv���B�f�[�^���������m�͂Ȃ����A���ۊe�z�X�g�����ݒ肷�鎝���\�ȊJ����ړI�Ƃ�����E�w�W�ɓ��B�����ɋ��ۂ��ꂽ�v���W�F�N�g�Ƃ����̂��H�L�ł���A�Ƃ����̂����g�����������Ă���CDM��ʂ��Ă̈�ۂł���B
�ł�CDM���x�͎����\�ȊJ���𑣂����Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��낤���B�����ւ̓��͂���Ǝv���B�C���h�l�V�A�ł͎����\�ȊJ���Ɍ����Ċ�]�̎��Ă銈�������Ă���CDM�v���W�F�N�g������A�����͏�L�̂S�̒�߂�ꂽ��̂��ׂĂɂ����ăR���v���C�A���X�ȏ�̊��������Ă���A���ʂ��邱�Ƃ́i�P�j�Q����Ƃ̃R�A�r�W�l�X��ϋɓI�ɗ��p���Ă���A�����āi�Q�j�n���R�~���j�e�B�Ƃ̘A�g�̋����A�̓�̗v���ł���B
�����̃v���W�F�N�g�̂����̈�͍��L��ƂŐΖ��E�K�X��Ђł���v���^�~�i���N�ސE�����Ј����W�܂���ꂽLPG(�t���Ζ��K�X)�̉�Ђ̃v���W�F�N�g�ł���B����͒n�������̂Ƃ̘A�g���������A�n���R�~���j�e�B���痦�悵�čH��ٗp���A���̒��̗D�G�҂ɂ͏��w����^�������̐��Y�H��̃}�l�W���[�Ƃ��Ĉ琬���A�P�Q�N��Ɏ����̂ւ̍H��̈Ϗ���ڎw���āA���̂Ƃ��ɂ��̎����̂�����������LPG�̐��Y�Ǘ����ł���悤�ɐϋɓI�Ȕ\�͈琬�Ɏ��g��ł���Ⴊ����B�����ЂƂ̗�ł͎����̂Ƃ̋����A�g�̐��̂��ƁA�n���R�~���j�e�B����̑�K�͂Ȍٗp���n�߂Ƃ��āA�S�~������̋ߑ㉻�A�����ĉ���������^���K�X������ꂽ�d�͂p���邱�ƂŎ����̂̎������𑝂₵�A�܂��R���|�X�e�B���O��������[���E�F�C�X�g�i���݃[���j�Ɍ����Ď��g��ł���v���W�F�N�g������B
���̂ق��ɂ��v���W�F�N�g�ł��܂��N���W�b�g�̐����������̂ɊҌ�����p�[�g�i�[�V�b�v��g��ł���v���W�F�N�g������ق��A�Ôg�̔�Вn�ɂ����Ēn�����{�Ƌ��ɒn���ɉ��ΔR���̎g�p�����炷�R���ϊ��ւ̃v���W�F�N�g�𐄐i���Ă���N�ƉƂ�����B
�����Ă����̃v���W�F�N�g�ɋ��ʂ���̂���Ƃ̃R�A�r�W�l�X�̗��p�A�����Ēn�������́E�R�~���j�e�B�Ƃ̗͋����A�g�ł���B����͂悭�݂���悤��CSR�Ȃǂ́A���Ƃ��Ċ�Ƃ̎��R�A�r�W�l�X�Ƃ͊W�̂Ȃ��`�����e�B�����ł͂Ȃ��A�܂��C�O��Ƃ������A�Z�p���x������̂͂������n���R�~���j�e�B���o�C�p�X���邱�Ƃł��e�ՂɃN���W�b�g���l�����悤�Ƃ���悤�Ȃ��̂ł��Ȃ��ACDM���x���ϋɓI�Ɏ����\�ȊJ���Ɍ������ė��p����Ă���Ƃ����P�[�X�ł���Ƃ�����B
���Ƃ��Ί��Ǘ��Ɣ��ɖ��ڂɊW�������Ă���h�Ђ̕���ł������̓�̗v�f�����˔�������Ɗ������o�Ă��n�߂Ă���B���z��k�Ђ̔�Ђ����P�Ƀz�[���Z���^�[����ƃR�����������グ��NPO�̊����ł́A�S���e�n�ŗL�u�̎����̂����Ċ�Ƃ��芈�����Ă���B�܂��t�����X�n�̎�ɃZ�����g�𒆐S�Ƃ��錚�ݎ��މ�Ђł������t�@�[�W���̓A�`�F�̒Ôg�̔��N��ɂP�O�O���~�߂����������n�ōs���A�n���ƘA�����A����̃R�A�r�W�l�X�̒ʂ��������I�ȃp�[�g�i�[�V�b�v�𐋍s���Ă���B�܂��t�B���s���ł�CNDR�i�ЊQ���ƃl�b�g���[�N�j�Ƃ�������P�O�N�ȏ�̊����𑱂��Ă���A�L�u�̊�Ƃ��W�܂�ϋɓI�ɒn�������̂Ƃ̘A�g���Ƃ�A�ЊQ���X�N�y���Ɍ������ϋɓI�Ȋ����𑱂��Ă���B
�������CDM�̊������ǂ��܂Ŋ�ƂɂƂ��Ă��̂悤�Ȗh�Ђ̕���ł݂��銈���ɋ߂Â��Ă�����̂��Ƃ������͂��邪�ACDM�Ƃ����A�J�[�{���N���W�b�g��ʂ��Ď��ۂ̎����������\�ƂȂ鐧�x�ɂ����Ă͊�Ƃ̃R�A�r�W�l�X�A�����Ēn�������̂Ƃ̗L�@�I�ȘA�g�͍��܂ł̕�������\���������̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B
���ۂ̎��g�݂Ƃ��āA�グ���邱�Ƃ́F
�i�P�j��ƊԂł̋���E�c�̂�����
�����CDM�����ɂ�����K�v�ƂȂ�Z�p��L���Ă����Ƃ��O�����Ă��܂�A�n���R�~���j�e�B�E�����̂���o�Ă���j�[�Y�ɓ�����悤�Ɏ���̃R�A�r�W�l�X�𗘗p����������ڎw�����̂ł���B����͗Ⴆ�Γ��{�̌o�ς��x���钆����Ƃ�ΏۂɁA���̗L�u�̊�Ƃ̋Z�p�Ȃǂ̃f�[�^�[�x�[�X���쐬���A�r�㍑�����p�ł���悤�ɂȂ�Ɣ��ɉ��l������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�i�Q�j�v���W�F�N�g�쐬��n�������̂���n�߂�
�C���h�l�V�A�Ŏ����\�ȊJ���Ɍ����ď����ɐi��ł���ƌ�����v���W�F�N�g�͂��̂��ׂĂŒn�������̗̂͋������[�_�[�V�b�v�A�Ƃ����̂�����BCDM�͖��Ԋ�Ƃ��i���̃t�@���h���Ǘ����Ă��鍑�ۑg�D�����悵�Ă���A�Ƃ����C���[�W���������A�����\�ȃv���W�F�N�g���l����ƁA���ڂ܂��n�������̂Ƃ̑Θb��i�߂Ă����A�������Ղɂ��ăv���W�F�N�g�쐬�ɂ������ށA�Ƃ������Ƃ���������Ȃ��B����ɂ͐��E�̒n�������̂̃l�b�g���[�N���`�����Ă��鍑��NGO�Ȃǂ��������݂��Ă��邽�߁A�����̑g�D�Ƃ̘A�g�������Ƃ��Ă������Ƃ��\�Ǝv����B
�i�R�j�v���W�F�N�g�J���ґ��ɗ��������_����������
CDM��ʂ��������\�ȊJ���A�Ƃ������Ƃ��ő���ɍl�����Ă�����g�݂̂ЂƂ��S�[���h�X�^���_�[�h�A�Ƃ������x������B����͂��̐��x��ʂ��ĊJ������A�����Ă��܂ꂽ�N���W�b�g�ɂ̓v���~�A�����A�ʏ�̃N���W�b�g�̒l�i�Ɣ�ׂč����l�i�Ŏ�������A�Ƃ������݂ł���B����͂��v���W�F�N�g�J���ґ��̗���ɂ��������̂ł���B�܂�UNDP�ł���N��MDG�J�[�{���t�@�V���e�B�Ƃ����A���~���j�A���J���ڕW�̎����ɍv������CDM�v���W�F�N�g���J�����Ă������Ƃ������g�݂��n�܂��Ă���A�z�X�g���ł̊J���̌��ʂ�������悤�ȃv���W�F�N�g�𗦐悵�ĊJ�����Ă������Ƃ��Ă���B
�ȏ�A�M�҂����܂ł����C���h�l�V�A���ɂƂ���CDM�Ƃ������x�𗘗p���A�ǂ̂悤�ȕ��@��ʂ��A���CDM�̂����ЂƂ̖ړI�ł���A�z�X�g���ɂ����鎝���\�ȊJ���ɂȂ��Ă�����̂��A�Ƃ������Ƃ��l�@���Ă݂��B�������C���h�l�V�A�ꍑ�ł̌��ʂŁA���ꂪ�A�W�A�S�́A�܂����E�S�̂ɓK�p���ꂽ�Ƃ��ɂǂ̂悤�ȏȂ̂��A�Ƃ�������ɂ͎c�O�Ȃ��琄���̈���o�Ȃ��̂����݂̂Ƃ���ł���B���g��CDM�Ƃ������ɓ��������肪���̕���Ɋւ�点�Ă�����Ă܂��܂��Ԃ��Ȃ��B���͂��������Ƃ͒p���������Ƃ��A�Ƃ͂悭���������g�A���̂悤�ȋC���ł���B�F�l�̎��B����A�Ȃ�炩�̌`�ł���������K���ł���B
�{�y�[�W��������������͂����炩��ǂ����@�ˁ@�����̃y�[�W�������
*�V�����y�[�W���J���̂ŁA���̃y�[�W���u���E�U�̈���{�^���ň�����ĉ������B
2008�N3��3���f��
�S���F�����A����A�{���A���V�A���c�A����
�@



