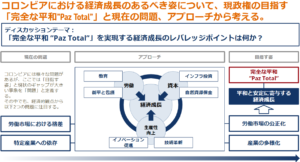コロンビア・スタディ・プログラム - 報告書「渡航中:その他街歩き(COMUNA13・コーヒー組合・グアタペ)」
Comuna13
要約
Comuna 13(コムナトレッセ)は、メデジン市内に位置する地区で、かつて暴力や犯罪が蔓延していたが、現在は劇的な復興を遂げた地域として知られる。2002年の「オリオン作戦」による治安回復後、ストリートアートやヒップホップ、観光業を通じて文化的・経済的再生が進められた。壁画やグラフィックアートは、過去の困難や希望を象徴し、観光客にとって大きな魅力となっている。また、屋外エスカレーターやケーブルカーの設置により、住民の生活環境や交通アクセスが改善された。現在、Comuna13はアートや文化を通じて平和と希望を発信し続けるとともに、観光地として地域経済を支える重要な役割を果たしている。
1.現地の概要
Comuna 13は、かつては麻薬取引や暴力組織の活動が横行し、国内で最も危険な地域の一つとされていた。2002年10月には「オリオン作戦」と呼ばれる政府の治安回復作戦が実施され、暴力組織の排除が図られたが、多くの市民が犠牲となり、人権侵害が深刻な問題となった。同作戦はコロンビアの武力紛争において都市部で行われた最も大規模な作戦であり、政府は左派ゲリラを標的としていたと主張するが、左派ゲリラとは無関係の大勢の住民も死亡または失踪した。
近年、この地区は劇的な復興を遂げ、ストリートアートやヒップホップ文化の中心地として注目を集めている。特に壁画アートは地域の歴史や住民の希望を象徴するものであり、多くの観光客を惹きつけている。2011年には屋外エスカレーターが設置され、急勾配の地形に住む住民の移動が大幅に改善された。この取り組みは、観光客を呼び込む契機ともなった。現在、コムナ13は歴史ツアーや文化体験を提供する観光地として地域経済に貢献している。一方、観光客の急増に伴う影響や依然として残る貧困といった課題も存在する。Comuna13は、暴力と困難を乗り越えた復興の象徴であり、希望と変革のメッセージを世界に発信している地区である。
2.現地で取り組まれているコロンビアの課題
まず挙げられるのが、貧困と社会的不平等の問題である。Comuna13の住民の多くは依然として貧困状態にあり、教育や医療、就労機会へのアクセスが十分ではない。同地における観光業の発展により一部の住民は収入を得ているが、利益の分配が不均衡であり、地域全体の経済的向上には至っていない。
次に、暴力・治安面やそれにともなう心理ケアである。過去のような広範な暴力は減少したものの、依然として一部の犯罪組織が活動しており、小規模な暴力事件や麻薬取引が散発的に発生している。これにより、住民の安全確保にも課題が残っているといえる。さらに、過去の暴力と軍事作戦によるトラウマが、地域社会に深い影響を与えている。特に高齢者や過去に暴力の被害を受けた住民の心のケアが十分でない現状がある。
そして、観光客の急増に伴うオーバーツーリズムも、浮上している課題の一つである。観光客の増加が地域文化の商業化を招き、住民の生活に悪影響を及ぼしているとの指摘がある。観光収益が一部の事業者に集中し、地域全体の利益にならないという指摘もある。また、エスカレーターや観光インフラの整備は注目を集めているが、これらの維持費用やさらなる整備のための資金確保が課題である。地域の住民の生活環境全般を改善するためには、より広範なインフラの整備が必要とされている。
3.現地でのプロジェクトの内容
現地で取り組まれているプロジェクトとして、①アートや文化への支援(グラフィックアート、ストリート・パフォーマンス)と、②インフラの整備(ケーブルカー、エスカレーター)が挙げられる。
アートや文化への支援
Comuna13のグラフィックアートやストリートパフォーマンスは、地域の復興と文化的アイデンティティを象徴する重要な要素である。グラフィックアートでは、壁画が地域の暴力的な過去や住民の困難を描きながら、平和や希望、連帯を訴えるメッセージを発信している。カラフルで力強いデザインは地域の個性と創造性を表現し、多くの観光客を惹きつける大きな魅力となっている。これらのアートは、地域のアーティストや住民にとって自己表現の場でもあり、アイデンティティの強化と外部へのメッセージ発信の手段として機能している。
一方、ストリートパフォーマンスはヒップホップやレゲトン、ブレイクダンス、詩の朗読などを中心に展開されており、観光客や地元住民を魅了している。これらのパフォーマンスは、過去の暴力や困難を乗り越えた経験を語るとともに、平和と希望を発信する場でもある。即興ラップやダンスは若者たちの自己表現の場となり、詩や物語の朗読は壁画とともに地域の歴史や住民の思いを伝えている。これらの活動は、住民にとってトラウマの克服やコミュニティの一体感を強める役割を果たし、観光収益を通じて経済的支援にもつながっている。
インフラの整備
Comuna13におけるインフラ開発の象徴として、ケーブルカーと屋外エスカレーターの整備が挙げられる。ケーブルカー(Metrocable)は、急勾配の地形に住む住民が市中心部にアクセスしやすくするために導入された公共交通機関で、通勤や通学の時間を短縮し、移動の負担を軽減した。また、観光客にとっても便利な移動手段であり、Comuna13を訪れる際のアクセスを大幅に向上させた。このシステムは、環境に優しい公共交通としても評価されている。一方、屋外エスカレーターは2011年に設置され、地域内の急な勾配を移動する住民の負担を劇的に減らした。全長384メートルのエスカレーターは、徒歩では約30分かかる道のりを数分で移動できるようにし、特に高齢者や子どもにとって重要なインフラとなっている。このエスカレーターは、都市計画の革新的な取り組みとして世界的にも注目されている。ケーブルカーとエスカレーターは、地域住民の生活改善だけでなく、観光業の発展を支える基盤としても機能し、Comuna13の復興を象徴する重要な要素となっている。
4.参加者所感
いまや観光地として有名なComuna13。歩いていても危険な雰囲気はなく、夕方まで見学が楽しめる一見安全そうな場所だが、今回調べてみて改めて治安や貧困の課題について知ることができた。華やかな商業ゾーンの向こう側には、貧困層の人々の住居があったのかもしれない。それが不可視化されてしまっていることに、ハワイや沖縄をはじめ世界中で起きている、観光/商業開発により貧困・暴力・紛争など不都合な実態が隠されてしまう現象との共通点を感じた。他方、Comuna13のケーブルカーや屋外エスカレーターはとてもよく整備されていて、同地までのバスや鉄道でのアクセスの良さも含めて移動は快適であった。観光開発と地域のインフラ整備は表裏一体であり、両者のバランスを取りながら持続可能な発展を目指すことの難しさや重要性を身をもって学び考える機会となった。
引用文献
- 戦場からコロンビア屈指の観光地となった「コムナ13」の闇、トラウマにいまも苦しむ住民 URL: https://www.ganas.or.jp/20230909comuna13/
- メデジン第13地区: コロンビア最恐のスラムを変えたアートと文化の力 district 13 of Medellin. https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%B3%E7%AC%AC13%E5%9C%B0%E5%8C%BA-%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%93%E3%82%A2%E6%9C%80%E6%81%90%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%92%E5%A4%89%E3%81%88%E3%81%9F%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A8%E6%96%87%E5%8C%96%E3%81%AE%E5%8A%9B-district-13-Medellin-ebook/dp/B0BZQR9CQD/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2FGRWPUU5YEXR&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WgES3ky8fTxuN-WEZKa8wCQVsEg_z-3RRBs1mRueUw43BoUxuoZ2jY9DaP3nXPhrhEWx0GmQUjGxUxxOj23nRg.V11j1_XRdq-M2Lh6DgFq41_VZNCId2e2yGFBVF3t2rc&dib_tag=se&keywords=%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%B3%E7%AC%AC13%E5%9C%B0%E5%8C%BA&qid=1736582974&s=digital-text&sprefix=%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%B8%E3%83%B3%E7%AC%AC13%E5%9C%B0%E5%8C%BA%2Cdigital-text%2C258&sr=1-1
コーヒー生産組合(Tejipaz)
要約
Tejipaz(テヒパス)は、メデジン近郊のグラナダ市を拠点とする紛争当事者NGOである。Tejipazとは、スペイン語のTejer(織る)とPaz(平和)の造語で「平和を織りなす」という意味を持つ。内戦や暴力の影響を受けたコミュニティで、対話や共同作業を通じて社会的絆を再構築し、平和的共存を促進することを目的としている。主な取り組みには、国内避難民であった農業生産者から買い取ったコーヒー豆を使用したカフェの運営、壁画制作や伝統工芸などアートを通じた共同活動、若者向けの平和教育やリーダー育成が挙げられる。これらを通じて住民同士の信頼を取り戻し、持続可能な平和を目指している。
1.機関の組織概要
Tejipazはコロンビアのグラナダ市民の願いから生まれ、平和を可視化し、コーヒー生産者を支援する目的で2016年に設立された。グラナダ市はアンティオキア東部で戦争の惨禍を最も受けた自治体の一つである。かつての内戦で荒廃した地域だった同市の山村は、近年情勢が安定し、離れていた住民も戻りつつある。彼らの多くはコーヒー生産に従事しており、Tejipazはそのコーヒーを商品化し、地域経済を支えている。グラナダ市の気候はコーヒー生産に適しており、コーヒーは輸出だけでなく、地元消費も盛んである。Tejipazの関係者によれば、環境的、社会的、経済的に優れたコーヒーを作ることが目標である。グラナダのコーヒーは味わいも多様で、甘いコーヒー、スッキリしたもの、濃い味や蜂蜜風味のコーヒーが楽しめる。これらのコーヒーは、グラナダ全体で平和の象徴として愛されているという。
2.機関が取り組んでいるコロンビアの課題
Tejipazの発祥地であるグラナダ市は、過去に深刻な紛争被害を受けており、これに起因する住民に根付く恐怖、限られた雇用機会、大規模な強制移住が、コミュニティの課題であった。同時に、これらを解決することがTejipazの設立を促した要因となった。したがって、Tejipazでは紛争被害者である当事者が中心となって、同じように紛争被害を受けてきたコーヒー農家や住民を支援することに重きを置いている。また、コーヒー農家には元兵士なども含まれている。
3.機関が取り組んでいるプロジェクトの内容
Tejipazは農産物の生産者と消費者を直接つなぎ、フェアな価格での取引を促進することで、農家の生活向上に寄与している。また、世帯主として働く女性らや障害者、若い起業家など、多様な背景を持つ約614の家族が直接的または間接的に関与している。さらに、約20人の元戦闘員が社会復帰の一環として農業に従事し、平和構築に貢献している。このようにTejipazの取り組みは、農業生産の向上だけでなく、社会的な和解と平和の象徴としての役割も果たしており、これによりグラナダは内戦の傷跡から立ち直り、平和と繁栄を目指す地域のモデルケースとして注目されている。
4.参加者所感
Tejipazを設立したクラウディア・ヒラルドとは、2016年にグラナダ市を初めて訪れた時に知り合ったが、その時はまだTejipazは存在せず、彼女は4月9日に行われた「紛争犠牲者の日」の行進イベントの参加者の一人であった。父親を紛争で失った彼女は、片手に花を携えながら父親へのメッセージをペイントしていた。きっとその時からTejipazの構想をすでに胸に温めていたのだろう。Tejipazの背景についてのインタビュー記事で、クラウディアは、紛争被害を受けた当事者が作るNGO「Asovida(アソヴィーダ)」に言及しながら、「AsovidaがなければTejipazは存在しなかった」と語っている。Asovidaは紛争犠牲当事者が、「支援される側から支援する側へ」という理念のもと立ち上げ、紛争記念館を運営し、紛争犠牲者の日のイベントも同団体が主催の一つとなり行ってきた。こうした紛争当事者の一つ一つの取り組みが、他の当事者団体に影響を与えながら発展していく様子を目の当たりにできたことは、非常に感慨深い。実際にTejipazは、運営側も紛争被害者でありながら、紛争当事者であるコーヒー農家の支援を通じて地域経済の活性化に貢献しており、Asovidaが掲げた「支援される側から支援する側へ」という理念は、蝶の羽ばたきの連鎖のように他に影響を与えながら、実現されつつある。
引用文献
- Tejipazホームページ URL: https://tejipaz.com/
- Hacemos Memoria URL: https://hacemosmemoria.org/2022/04/27/tejipaz-el-emprendimiento-de-los-sobrevivientes-de-granada/
グアタペ
要約
グアタペは、コロンビアのアンティオキア県に位置する美しい町であるが、過去には国内紛争の影響で住民の多くを失った歴史を持つ。グアタペにおける暴力の時代は、コロンビア全土で続いた内戦や麻薬取引の影響を受け、20世紀後半から2000年代初頭にかけて特に深刻化した。この期間、左翼ゲリラや右翼民兵組織、麻薬カルテルが地域で活動し、住民は暴力や強制移住の被害を受けた。しかし、近年の和平プロセスの進展により、治安は大幅に改善され、現在では観光地としての魅力が再評価されている。グアタペは、カラフルな街並みや自然景観で多くの観光客を引きつけており、過去の困難を乗り越えた地域として注目されている。
1.現地の概要
グアタペは、メデジンから車で約2時間の距離に位置する。人口約9,000人のこの町は、カラフルな建物と独特の装飾「ソカロ(Zócalo)」で知られる。ソカロとは、建物の壁面下部に描かれるレリーフで、動物や風景、伝統的な模様などが多彩にデザインされ、町全体に色鮮やかな景観を生み出している。近郊には「ピエドラ・デル・ペニョール(El Peñón de Guatapé)」と呼ばれる高さ約200メートルの巨大な岩があり、岩に設置された740段の階段を上ると、美しい湖と島々の絶景を一望できる。また、1970年代に水力発電用のダムが建設されたことで複雑な形状の湖が形成され、ボートツアーやウォータースポーツなどの観光アクティビティが盛んである。グアタペは、そのカラフルな街並みと自然景観、観光アクティビティの豊富さで訪れる人々を魅了している。
他方、グアタペ周辺の農村地域では、左翼ゲリラや右翼民兵組織、麻薬密売組織などが活動し、住民は暴力や強制移住の被害を受けた。しかし、近年の和平プロセスの進展により、地域の治安は改善し、観光地としての魅力が再評価されている。現在、グアタペはそのカラフルな街並みや自然景観で多くの観光客を引きつけているが、ダム建設時の住民の強制移住問題を含めて、過去の紛争の歴史を忘れず、平和と安定の重要性を再認識することが求められている。
2.現地で取り組まれているコロンビアの課題
グアタペは1990年代後半から2003年にかけて、東アンティオキア地域で発生した暴力の影響を大きく受けた場所の一つである。この時期、ゲリラと準軍事組織が戦略的な地域を巡って争い、グアタペもその一つであった。またこのような歴史的背景を持つグアタペでは、ソカロ(壁画)を通じて地域の歴史や文化を学ぶ取り組みを行っている。「グアタペ広場」には、15×15メートルの巨大なソカロが設置され、グアタペの歴史や美しさ、地域性を表現している。このプロジェクトは、地域のアイデンティティを強化し、訪問者にグアタペの文化を紹介することを目的としている。グアタペの壁画は、町おこしの一環として、地域のアイデンティティを強化し、観光業の活性化に寄与している。国内避難民やコミュニティの復興はコロンビア全土に共通する課題であるが、グアタペはカラフルな街並みの構築により町おこしを成功させ、これらの課題を克服したモデルケースである。
3.現地でのプロジェクトの内容
グアタペの家々の壁面を彩る「ソカロ」は、独自の歴史と文化を物語っている。これらの装飾は、もともと湿気や動物から壁を保護するために設置されたが、次第に住民の生活や信仰、伝統を描く芸術作品へと発展した。1920年代、ホセ・マリア・パラ・ヒメネスが、宗教的なシンボルである子羊のシルエットを自宅の内部に描いたことから、装飾としてのソカロの伝統が始まった。このデザインは保守的でカトリックの強い町で広まり、多くの家で採用された。
1970年代、メデジンの電力供給を目的としたダム建設により、グアタペの70%が水没し、農業中心の経済が大きな打撃を受けた。しかし、住民たちは団結し、町の再建に取り組んだ。ソカロの装飾は、町の美化と観光促進の手段として再評価され、各家庭が独自のデザインを施すようになった。これにより、グアタペは「ソカロの町」として知られるようになり、観光地としての地位を確立した。しかし、近年の都市開発と観光客の増加により、ソカロの伝統が危機に瀕している。高層建築の増加や観光地化に伴い、ソカロの保存が難しくなっている。これに対し、地元の行政や文化団体は、ソカロの保護と伝統の継承に向けた取り組みを進めている。グアタペのソカロは、町の歴史、文化、そして住民の抵抗と再生の象徴として、今もなお重要な役割を果たしている。
4.参加者所感
カラフルな街並みで知られるグアタペは、メデジンからアクセスのよい日帰り観光地としても有名だが、地元の人々からは1970年代のダム建設にともなう住民の強制移住や、その後の「暴力の時代」における悲惨な歴史の苦悩を聞くことも少なくない。一見、別々の事象に見えるが、両者は国家によるエネルギー政策という点で実はリンケージしている。グアタペの近隣に位置するグラナダ市の紛争当事者NGO「Asovida」の関係者は、スタディーツアーで訪問した際に、アンティオキア県はコロンビアの主要なエネルギー産地であり、その大部分がグアタペやグラナダの位置する東部に依拠していたため、これらの地域が紛争の際に標的にされやすくなったと語っていたのが印象的だった。エネルギー政策は経済や環境問題の観点から議論されがちだが、地域安全保障の観点からも今後は考察していく必要があると考えるようになった。
引用文献
- El Universal URL: https://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/2021/08/15/guatape-el-pueblo-donde-las-paredes-hablan.com
- El Colombiano URL: https://www.elcolombiano.com/antioquia/guatape-los-zocalos-y-sus-historias-de-la-resistencia-CX9808127