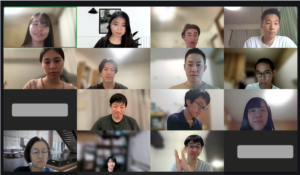コロンビア・スタディ・プログラム - 報告書「渡航前:第2回勉強会」
発表概要
第2回勉強会では、「コロンビア基礎編」として、環境・社会・経済の観点からコロンビアに関する幅広い知識を学び、得た知識をもとにコロンビアに関する仮説への考えを深める機会を作ることとした。
環境セッションでは、コロンビアの地理や気候、自然災害や防災政策、豊富な天然資源の埋蔵状況やエネルギー利用動向を解説するとともに、コロンビアが生物多様性条約締約国会議(COP)の次回会合をホスト国としてリードしている旨を紹介した。社会セッションでは、コロンビアの建国後の内戦や和平交渉の歴史、国内避難民やベネズエラ難民に対する対応などを紹介した。経済セッションでは、石油・石炭、コーヒーなどの特定産業に依存する産業構造や労働市場における格差について紹介するとともに、コロンビア政府や国際機関などが推進する教育政策やインフラ開発事業、紛争地域の女性の自立支援政策などを解説した。3つのセッションでは、有志メンバーが事前にコロンビアの各セクションの状況について調査し、他のメンバーに対して知見を共有することで各自の仮説を深堀りしていく契機となった。
ディスカッション
第2回勉強会では、環境・社会・経済のテーマ別ディスカッションにくわえ、各メンバーが事前に準備した仮説について議論する個別ディスカッションを行った。
- テーマ別ディスカッション
- 環境面では、先進国主導で策定する環境指標を新興国に適用することが適切なのか、都市部と農村部の格差是正のための開発プロジェクトが環境問題を悪化させることに繋がりかねないのではないか、などの議論があった。
- 社会面では、難民と受け入れ国の双方の視点からどのような課題があるのかについて、医療や治安、教育などの個別論点を議論した。
- 経済・産業面では、採掘産業から脱却して製造業や観光業などの新たな産業を育成する方法はあるのか、イノベーションを促すための具体的な取組みはあるのか、などの議論が行われた。
- 個別ディスカッション
- コロンビア特有の地域間格差として地形や内戦、インフラ格差などに着目して、現地では、環境と経済発展のバランスや都市部から見た地方の課題に着目したいとの意見があった。
- 難民の子供の教育について、不十分な教育アクセスや脆弱なインフラ環境により、次世代の自立の阻害要因になっているのではないかとの意見が出た。
- 武装勢力の社会復帰に向けた支援は重要である一方、その他の社会的に脆弱な立場の人たちから支援が不公平と思われるのではないかとの声も聞かれた。
- コロンビア政府が環境問題で国際的にリードしている一方、再生可能エネルギーの導入が進んでいない現状を踏まえると、豊富な資源を背景に国内でボトルネックがあるのではないかとの意見があった。
参加者所感
第2回勉強会では、環境・社会・経済の幅広い観点からコロンビアに関する基礎的な知識を学び、第3回以降の勉強会や現地渡航に備える有意義な機会となった。各セッションのテーマは非常に幅広い内容であり、第3回以降の勉強会で個別の詳細テーマを取り扱うこととなったが、第2回勉強会で基礎知識を学んだことにより、各メンバーはそれぞれの興味関心のある分野について理解を深め、仮説に対する考えを再考する良い機会となったのではないかと感じた。
※最後に写真(オンラインMTGの様子)を掲載